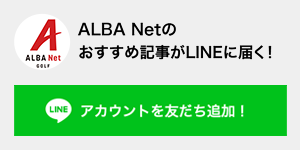<日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills 最終日◇9日◇宍戸ヒルズカントリークラブ(茨城県)◇7,387ヤード・パー71>
日本の男子ゴルフ界にとって、ここまでどんな1年だったのだろうか。あっという間に過ぎたのか、それともようやく1年なのだろうか。2018年5月、男子ゴルフ界へ逆風が吹いた片山晋呉の“プロアマ問題”。最後は片山本人が記者会見を開いて謝罪し、徐々に騒動も収まっていったが、あらためて「プロゴルファーとしての在り方」を問われたのは間違いない。丸1年を迎えた同大会に対し、ツアー機構側、そして選手はどんな思いで臨んだのか。
謝罪会見にまで発展する事態となった【写真】
日本ゴルフツアー機構会長の青木功は、「自分たちの職場を見られる、見てもらう立場として表現していってほしいというのが私の目的。今まではそういうきっかけを作ってあげられなかった」と語る。「プロアマでも今までは積極的な会話がなかったが、“なにか聞きたいことがありますか”と言えるくらいになりなさいと伝えている。ちょっとした会話でもいい。選手側も心を開けて、ボランティアやギャラリーのかたがたにも来て良かったと思ってもらえるような環境に自然になればいい。そのためにも、のびのびと自分をアピールできる場所や、表現できる場をつくりたい」。青木は日頃から、若手選手たちに個性を出すことを訴えているという。「自分が主役だと思うこと。ひとりひとりの強い個性が融合した時に大きな力に変わっていき、ツアーの活性化につながっていく」。
青木の思いに対し敏感に反応したのが、下部のAbemaTVツアーに参戦してきた若手選手たちだ。QTランク36位の資格でレギュラーツアーにスポット参戦している鍋谷太一は、「僕らはある意味でまだ “値打ち”はなくて、自分をなるべく売り出したいという考えがある」と語るそばから、集まったファンを軽快なトークで楽しませていた。
「ファンがあって、スポンサーがあっての自分たち。プレーで良いところが見せられなくても、ファンサービスでカバーする。そうすれば自分もまた頑張ろうと思える」。鍋谷をはじめ中里光之介、中西直人など、レギュラーツアーでまだなじみがない選手にもかかわらず、スタートティでの歓声やサインを求めるファンの姿は多かった。今後のゴルフ界を担う世代が危機感を持ち、そこを中心に変わり始めている証だろう。
下部ツアーの選手たちがこうした意識を持つのは、昨年からインターネットテレビの「AbemaTV」が同ツアーのスポンサーについたことも一因となっている。全試合をネットテレビで中継、ホールアウトした選手を続々と放送席に呼んでインタビューを行い、これが強烈なメディアトレーニングとなっている。「レギュラーに来ても、慣れたうえで自分のゴルフができる。AbemaTVに加わっていただいてありがたいし、育てていただいているのでありがたい。選手たち自身もやってもらっているというありがたさもわかる」(青木)。
これ以外にも男子ツアー全体で昨シーズンからSNSでの情報発信や試合会場での公開インタビュー、レッスンイベントなど、さまざまな場面で選手が自らの言葉でファンやスポンサーと接触してきた。公式インスタグラムでは、練習中の動画LIVE配信や“インスタ映え”を意識した写真を投稿。今季からはスポーツコンテンツ配信サービスの『スポーツナビ』に1日に3本ほどニュースや動画を配信し、週で800万近くのPVはこれまでの倍以上の成果となった。本大会でも、本戦中のコース内での写真撮影可能エリアが日本では初めて本格的に導入されるなど、選手を露出する機会を積極的に作っている。
「プロとして責任を果たし、ゴルフもきちんとやりながらファンにもきちんと接する。メディアにもきちんと接する。それをどう機構としてサポートしていくか」(青木)と奮闘を続ける男子ツアー。とはいえ、現状を考えると人気が急激に回復するとは考えられず、今後を担う若手選手が作り始めた波に、上の世代がどう乗っていけるかが課題となるだろう。ツアーに20年以上籍を置くベテラン選手の間でも、「日本ツアーは規制が多い中で、いろいろ取り組みを行っていると思う。でも、まだまだやれることは当然ある」と、若手に触発されるように少しずつながら意識改革が進んでいる。
1990年代は年間40近い試合が行われていたが、今季は米ツアーとの共催大会「ZOZO CHAMPIONSHIP」を含めて25試合。ZOZO CHAMPIONSHIP、そして約1年後に迫った東京五輪と注目度が高まっているが、その追い風がなくなったときにどう転ぶか。あれから1年が過ぎ、危機感を強く持って動いてきた。男子ツアー広報担当の佐藤信人は「様々な面で種をまいてきた」と表現する。ここまで行ってきたことを精査する段階だと語ったが、その種はどう花開くのだろうか。これからの1年を“まだ1年”とみるか、“1年しかない”と見るか。答えはともかく、少なくとも後者の危機感で臨まないと男子ツアーの視界は開けてこない。(文・谷口愛純)
日本の男子ゴルフ界にとって、ここまでどんな1年だったのだろうか。あっという間に過ぎたのか、それともようやく1年なのだろうか。2018年5月、男子ゴルフ界へ逆風が吹いた片山晋呉の“プロアマ問題”。最後は片山本人が記者会見を開いて謝罪し、徐々に騒動も収まっていったが、あらためて「プロゴルファーとしての在り方」を問われたのは間違いない。丸1年を迎えた同大会に対し、ツアー機構側、そして選手はどんな思いで臨んだのか。
謝罪会見にまで発展する事態となった【写真】
日本ゴルフツアー機構会長の青木功は、「自分たちの職場を見られる、見てもらう立場として表現していってほしいというのが私の目的。今まではそういうきっかけを作ってあげられなかった」と語る。「プロアマでも今までは積極的な会話がなかったが、“なにか聞きたいことがありますか”と言えるくらいになりなさいと伝えている。ちょっとした会話でもいい。選手側も心を開けて、ボランティアやギャラリーのかたがたにも来て良かったと思ってもらえるような環境に自然になればいい。そのためにも、のびのびと自分をアピールできる場所や、表現できる場をつくりたい」。青木は日頃から、若手選手たちに個性を出すことを訴えているという。「自分が主役だと思うこと。ひとりひとりの強い個性が融合した時に大きな力に変わっていき、ツアーの活性化につながっていく」。
青木の思いに対し敏感に反応したのが、下部のAbemaTVツアーに参戦してきた若手選手たちだ。QTランク36位の資格でレギュラーツアーにスポット参戦している鍋谷太一は、「僕らはある意味でまだ “値打ち”はなくて、自分をなるべく売り出したいという考えがある」と語るそばから、集まったファンを軽快なトークで楽しませていた。
「ファンがあって、スポンサーがあっての自分たち。プレーで良いところが見せられなくても、ファンサービスでカバーする。そうすれば自分もまた頑張ろうと思える」。鍋谷をはじめ中里光之介、中西直人など、レギュラーツアーでまだなじみがない選手にもかかわらず、スタートティでの歓声やサインを求めるファンの姿は多かった。今後のゴルフ界を担う世代が危機感を持ち、そこを中心に変わり始めている証だろう。
下部ツアーの選手たちがこうした意識を持つのは、昨年からインターネットテレビの「AbemaTV」が同ツアーのスポンサーについたことも一因となっている。全試合をネットテレビで中継、ホールアウトした選手を続々と放送席に呼んでインタビューを行い、これが強烈なメディアトレーニングとなっている。「レギュラーに来ても、慣れたうえで自分のゴルフができる。AbemaTVに加わっていただいてありがたいし、育てていただいているのでありがたい。選手たち自身もやってもらっているというありがたさもわかる」(青木)。
これ以外にも男子ツアー全体で昨シーズンからSNSでの情報発信や試合会場での公開インタビュー、レッスンイベントなど、さまざまな場面で選手が自らの言葉でファンやスポンサーと接触してきた。公式インスタグラムでは、練習中の動画LIVE配信や“インスタ映え”を意識した写真を投稿。今季からはスポーツコンテンツ配信サービスの『スポーツナビ』に1日に3本ほどニュースや動画を配信し、週で800万近くのPVはこれまでの倍以上の成果となった。本大会でも、本戦中のコース内での写真撮影可能エリアが日本では初めて本格的に導入されるなど、選手を露出する機会を積極的に作っている。
「プロとして責任を果たし、ゴルフもきちんとやりながらファンにもきちんと接する。メディアにもきちんと接する。それをどう機構としてサポートしていくか」(青木)と奮闘を続ける男子ツアー。とはいえ、現状を考えると人気が急激に回復するとは考えられず、今後を担う若手選手が作り始めた波に、上の世代がどう乗っていけるかが課題となるだろう。ツアーに20年以上籍を置くベテラン選手の間でも、「日本ツアーは規制が多い中で、いろいろ取り組みを行っていると思う。でも、まだまだやれることは当然ある」と、若手に触発されるように少しずつながら意識改革が進んでいる。
1990年代は年間40近い試合が行われていたが、今季は米ツアーとの共催大会「ZOZO CHAMPIONSHIP」を含めて25試合。ZOZO CHAMPIONSHIP、そして約1年後に迫った東京五輪と注目度が高まっているが、その追い風がなくなったときにどう転ぶか。あれから1年が過ぎ、危機感を強く持って動いてきた。男子ツアー広報担当の佐藤信人は「様々な面で種をまいてきた」と表現する。ここまで行ってきたことを精査する段階だと語ったが、その種はどう花開くのだろうか。これからの1年を“まだ1年”とみるか、“1年しかない”と見るか。答えはともかく、少なくとも後者の危機感で臨まないと男子ツアーの視界は開けてこない。(文・谷口愛純)