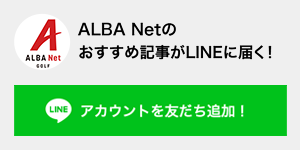台風襲来直前の強風が吹き荒れるレイクグリーンGC(岐阜県)18番。ジャンボに1打差をつけた合田の第2打は残り165ヤード。5番アイアンを振り抜いた感触は完璧だった。「20ヤードくらい奥のピンに軽いドローでかぶっていった。バーディーチャンスだ」と思ったのも束の間。ボールは、強烈なアゲンストに戻され、グリーン手前。バンカーにつかまった。ジャンボの第2打がグリーン手前の横の寄せやすいところにあるのを見て、一瞬、勝負をあきらめかけた。「オレ、勝てないんだ…」。だが、すぐに打ち消した。「『いや、まだ終わってない、終わってない』って言い聞かせていました。後でテレビの映像を見ると首を横に振っているのが映っている」。
決して難しいライではない。パーセーブして優勝するためには9番アイアンで寄せるのが最適なのはわかっていたが、ショートゲームは今一つ。様々な条件からはじき出した答えが、パターで寄せることだった。
「どんな状況でもいいスコアを出せることを一番に考えていた。すごいアゲンストの中で一番転がってくれると思った。パターならチャックリもない。生まれて初めてバンカーからパターで打った、ダメならボロカス言われるだろうけど、まあ、いいや」。そんな心境だった。
フックライン。上の段に切られたカップの1メートル右を狙った。打った瞬間、スーッと転がってピッタリだと感じた。ところが、強い風にさらされたグリーンは思ったより速く、2メートルオーバー。バンカーからパターで打ったことを記憶している人が圧倒的に多いが、実はこの返しこそ難易度の高いウイニングパットだった。
「軽いスライスに見えて軽いフック。練習ラウンドであの位置にピンが切られる可能性があると思ってラインは分かっていた。下(3位以下)とは離れていたから、4パットしても2位だし」とパーパットを鮮やかに決めて初優勝が決まった。
ジャンボと握手をした後の姿も、覚えている人が多い。ヘナヘナと力の抜けた合田を、ジャンボが抱えるように見えるシーンだ。だが合田は首を横に振る。「『カンベンしてくださいよ』と肩でジャンボさんにタックルしたつもり。それがヘナヘナになったみたいになっちゃって、ジャンボさんにハグされている(苦笑)」。
無敵の強さを誇るジャンボ相手に手にした初優勝は公式戦日本プロのビッグタイトル。当時は10年シードが付いてきた。85年にプロになり、87年以来ずっとシード権には手が届かないながらも月例や予選会(制度が途中で変わっている)や下部ツアーのグローイングでランキング上位に入る“裏シード”などでツアーに出場していただけに、名誉以上に「10年間、予選会に出なくてすむんだ」という思いがこみ上げた。
予選会44位。これがこの年の合田のステイタスだ。出場できる試合は限られている。研修生時代からライバルのように意識し合ってきた同い年の佐々木久行に先んじてきた自負も消えかけていた。予選会に失敗し「終わっちゃったのかな、オレ。久行に完全に抜かれちゃったな」という思いもあって迎えた年でもあった。
開幕戦「東建カップ」の舞台は親戚も多い鹿児島の祁答院CC。ウェイティングからの出場を狙い、初日のスタートを最後まで待ったが、あと1人で惜しくも出られなかった。その足で向かったのは、鹿児島市内。母方の祖母が危篤だった。叔母が一人で祖母を見ていた。やってきた孫に、祖母は何度もこう繰り返した。「お前は人を幸せにする力がある光の子だから、そう思って一生を全うしてくれ」。その日のうちに祖母は亡くなり、言葉は遺言となった。
東京オリンピックの開会式が行われた1964年10月10日生まれの合田が、29歳で迎えたシーズン。18歳で龍ヶ崎CCの研修生となり、20歳9日でプロテストに合格して以来、試合に出続けていた。「ずっとテンパり続けていたから、自分のゴルフを見つめ直す時期なのかなとは思っていた。ホントのトレーニングというものを知らず、お金もない。体のケアもわかっていない。いろいろわからなくなっていた。自分を見つめ直して、もう一度出て来るか、いなくなるかという感じ」と振り返る時期だった。
前年には長男が誕生し、麻里夫人のおなかの中には第二子がいた(9月30日に長女誕生)。父親としての責任ものしかかる。
そんな中で臨んだのが5月の日本プロだった。前の週からショットの調子が上向きになったのを感じ「ひょっとしたらいいかも」という予感もあった。セッティングが厳しいコースを見て、その思いはさらに強くなる。
予感は当たった。3日目を終わってトータル7アンダーで5打差単独首位。2位に海老原清治、1打遅れてジャンボがいた。
当時のジャンボは、6打差などモノともしないほどの強さを見せていた。ツアー優勝経験のない合田にとっては大きな大きな相手といえた。最終日は、季節外れの台風予報。「台風で最終日が流れないかな」という本音もないわけではなかった。
覚悟が決まったのは、伯父と約束を交わしてからだ。この週は、コースから約30分の伯父の自宅に泊まっていた。事情があって故郷の愛媛県に長いあいだ帰っていない伯父だった。祖父が亡くなった時ですら、説得しても戻らかったほど。祖母にかわいがられていた甥(合田)はそのことをずっと気にしていた。最終日を前にした夜、食事をしながら伯父にこう切り出した。「もし、オレがこの試合で優勝したら一緒に田舎に帰らんか」。伯父は、しばらく考えてからポツリと言った。「帰る…。勝ってくれ」。重い約束だった。
台風が当初の予報よりはるかに遅れ、最終日は予定通り行われた。「とにかくパターがよく入っていた」というジャンボはジワジワと差を縮めて来る。同じ組の海老原はじめほかの選手とは差が開き、合田VSジャンボのマッチプレーのような優勝争いとなった。
以前、一緒にプレーした大先輩、杉原輝雄に教えられた優勝争いの心得はよく覚えていた。「最終日の残り3ホールまでは(リーダー)ボードを見るな」ということ。しかし「俺のゴルフはもしかして今年で終わりかもしれない、最後かもしれないから」という思いがあってあえて逆らった。ボードは欠かさずチェックし、目の前のジャンボも意識した。
その上で「10年後を考えて自分のゴルフに集中した」という18ホール。集大成が、バンカーからのパターでの寄せと難易度の高いパーパットだった。これを乗り越えて、合田は見事に優勝した。
伯父は、合田の優勝を信じていた。優勝が決まると花束を持った従妹たちが現れたのがその証拠だ。約束はすぐには守られなかった。だが、しばらく経って「約束じゃから」と一人でそっと故郷に行ったことを、祖母からの電話で知った、「ありがとう」と泣きながら感謝された。
地獄に足を踏み入れたのは、両刃の剣である10年シードを手に入れたから。毎年、シード権を気にしなくていいことで、腰を据えてゴルフを建て直そうとすることが苦悩を生み出す。「プロだからあがくだけあがくけど誰も助けてはくれない。全部自分」という状態に陥ることになる。結果だけを求める周囲は「人の不幸は蜜の味」とばかり、勝手なことを吹聴し、本人や家族にまで余計な言葉を運んでくるからだ。10年間試合に出られることは、10年間試合に出なくてはいけないこと、と言い換えることもできる。例え稼げなくとも、出場の義務はある。金銭的に追い詰められた時期もある。
だが、そのすべてを乗り越えて、現在がある。「今考えれば(地獄を見たことも)いい人間修行になりました。どん底の下にはさらにどん底があることも知ったし、いい意味で新しい自分自身を作るための人間修行。踏みとどまれるのは自分しかいない」。日本プロ優勝で天国と地獄を味わった男は、そう言って笑顔を見せた。(文・小川淳子)
決して難しいライではない。パーセーブして優勝するためには9番アイアンで寄せるのが最適なのはわかっていたが、ショートゲームは今一つ。様々な条件からはじき出した答えが、パターで寄せることだった。
「どんな状況でもいいスコアを出せることを一番に考えていた。すごいアゲンストの中で一番転がってくれると思った。パターならチャックリもない。生まれて初めてバンカーからパターで打った、ダメならボロカス言われるだろうけど、まあ、いいや」。そんな心境だった。
フックライン。上の段に切られたカップの1メートル右を狙った。打った瞬間、スーッと転がってピッタリだと感じた。ところが、強い風にさらされたグリーンは思ったより速く、2メートルオーバー。バンカーからパターで打ったことを記憶している人が圧倒的に多いが、実はこの返しこそ難易度の高いウイニングパットだった。
「軽いスライスに見えて軽いフック。練習ラウンドであの位置にピンが切られる可能性があると思ってラインは分かっていた。下(3位以下)とは離れていたから、4パットしても2位だし」とパーパットを鮮やかに決めて初優勝が決まった。
ジャンボと握手をした後の姿も、覚えている人が多い。ヘナヘナと力の抜けた合田を、ジャンボが抱えるように見えるシーンだ。だが合田は首を横に振る。「『カンベンしてくださいよ』と肩でジャンボさんにタックルしたつもり。それがヘナヘナになったみたいになっちゃって、ジャンボさんにハグされている(苦笑)」。
無敵の強さを誇るジャンボ相手に手にした初優勝は公式戦日本プロのビッグタイトル。当時は10年シードが付いてきた。85年にプロになり、87年以来ずっとシード権には手が届かないながらも月例や予選会(制度が途中で変わっている)や下部ツアーのグローイングでランキング上位に入る“裏シード”などでツアーに出場していただけに、名誉以上に「10年間、予選会に出なくてすむんだ」という思いがこみ上げた。
予選会44位。これがこの年の合田のステイタスだ。出場できる試合は限られている。研修生時代からライバルのように意識し合ってきた同い年の佐々木久行に先んじてきた自負も消えかけていた。予選会に失敗し「終わっちゃったのかな、オレ。久行に完全に抜かれちゃったな」という思いもあって迎えた年でもあった。
開幕戦「東建カップ」の舞台は親戚も多い鹿児島の祁答院CC。ウェイティングからの出場を狙い、初日のスタートを最後まで待ったが、あと1人で惜しくも出られなかった。その足で向かったのは、鹿児島市内。母方の祖母が危篤だった。叔母が一人で祖母を見ていた。やってきた孫に、祖母は何度もこう繰り返した。「お前は人を幸せにする力がある光の子だから、そう思って一生を全うしてくれ」。その日のうちに祖母は亡くなり、言葉は遺言となった。
東京オリンピックの開会式が行われた1964年10月10日生まれの合田が、29歳で迎えたシーズン。18歳で龍ヶ崎CCの研修生となり、20歳9日でプロテストに合格して以来、試合に出続けていた。「ずっとテンパり続けていたから、自分のゴルフを見つめ直す時期なのかなとは思っていた。ホントのトレーニングというものを知らず、お金もない。体のケアもわかっていない。いろいろわからなくなっていた。自分を見つめ直して、もう一度出て来るか、いなくなるかという感じ」と振り返る時期だった。
前年には長男が誕生し、麻里夫人のおなかの中には第二子がいた(9月30日に長女誕生)。父親としての責任ものしかかる。
そんな中で臨んだのが5月の日本プロだった。前の週からショットの調子が上向きになったのを感じ「ひょっとしたらいいかも」という予感もあった。セッティングが厳しいコースを見て、その思いはさらに強くなる。
予感は当たった。3日目を終わってトータル7アンダーで5打差単独首位。2位に海老原清治、1打遅れてジャンボがいた。
当時のジャンボは、6打差などモノともしないほどの強さを見せていた。ツアー優勝経験のない合田にとっては大きな大きな相手といえた。最終日は、季節外れの台風予報。「台風で最終日が流れないかな」という本音もないわけではなかった。
覚悟が決まったのは、伯父と約束を交わしてからだ。この週は、コースから約30分の伯父の自宅に泊まっていた。事情があって故郷の愛媛県に長いあいだ帰っていない伯父だった。祖父が亡くなった時ですら、説得しても戻らかったほど。祖母にかわいがられていた甥(合田)はそのことをずっと気にしていた。最終日を前にした夜、食事をしながら伯父にこう切り出した。「もし、オレがこの試合で優勝したら一緒に田舎に帰らんか」。伯父は、しばらく考えてからポツリと言った。「帰る…。勝ってくれ」。重い約束だった。
台風が当初の予報よりはるかに遅れ、最終日は予定通り行われた。「とにかくパターがよく入っていた」というジャンボはジワジワと差を縮めて来る。同じ組の海老原はじめほかの選手とは差が開き、合田VSジャンボのマッチプレーのような優勝争いとなった。
以前、一緒にプレーした大先輩、杉原輝雄に教えられた優勝争いの心得はよく覚えていた。「最終日の残り3ホールまでは(リーダー)ボードを見るな」ということ。しかし「俺のゴルフはもしかして今年で終わりかもしれない、最後かもしれないから」という思いがあってあえて逆らった。ボードは欠かさずチェックし、目の前のジャンボも意識した。
その上で「10年後を考えて自分のゴルフに集中した」という18ホール。集大成が、バンカーからのパターでの寄せと難易度の高いパーパットだった。これを乗り越えて、合田は見事に優勝した。
伯父は、合田の優勝を信じていた。優勝が決まると花束を持った従妹たちが現れたのがその証拠だ。約束はすぐには守られなかった。だが、しばらく経って「約束じゃから」と一人でそっと故郷に行ったことを、祖母からの電話で知った、「ありがとう」と泣きながら感謝された。
地獄に足を踏み入れたのは、両刃の剣である10年シードを手に入れたから。毎年、シード権を気にしなくていいことで、腰を据えてゴルフを建て直そうとすることが苦悩を生み出す。「プロだからあがくだけあがくけど誰も助けてはくれない。全部自分」という状態に陥ることになる。結果だけを求める周囲は「人の不幸は蜜の味」とばかり、勝手なことを吹聴し、本人や家族にまで余計な言葉を運んでくるからだ。10年間試合に出られることは、10年間試合に出なくてはいけないこと、と言い換えることもできる。例え稼げなくとも、出場の義務はある。金銭的に追い詰められた時期もある。
だが、そのすべてを乗り越えて、現在がある。「今考えれば(地獄を見たことも)いい人間修行になりました。どん底の下にはさらにどん底があることも知ったし、いい意味で新しい自分自身を作るための人間修行。踏みとどまれるのは自分しかいない」。日本プロ優勝で天国と地獄を味わった男は、そう言って笑顔を見せた。(文・小川淳子)