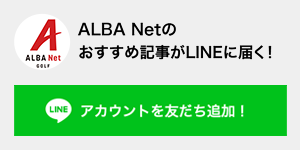第5回は中嶋常幸が「勝った試合の中では」の条件付きで、いの一番に挙げた名勝負。1990年10月7日、北海道初開催となった小樽CCでの日本オープン最終日を振り返る。
2メートルはあったパーパットが、カップへと吸い寄せられるようにグリーンを転がっていく。真っ白なボールがカップに消えた。その瞬間、北の大地を揺るがすような大歓声が、14番グリーンを包み込んだ。
この1発が、勝負の流れをガラリと変えた。ジャンボ尾崎の日本オープン3連覇を阻んだ1打を挙げるとするならば、中嶋が入れたこのパットだということになる。
3日目を終えて中嶋はいったん、勝負をあきらめかけた。首位を明け渡した相手は、ジャンボ尾崎。最終日の18ホールを残しての4ストロークは、絶望的な差に思えたからだ。
「とにかく、あの頃のジャンボは強かったからね」(中嶋)
国内最高峰の大会である日本オープン。中嶋は初日2位の好スタートを切って、2日目に首位に立ってトーナメント前半を折り返した。しかし3日目は、どんより曇った空に抑え付けられたかのように、自分のゴルフができなかった。首位を明け渡した原因は、中嶋の内にあった。「人を見ちゃダメなんだ」。
ライバルとの闘いに身を焦がし、自ら崩れてしまった3日目の18ホール。それは日本オープンと言う大舞台ではなく、戦っている目の前の相手が、当時最強の呼び声が高かった、ジャンボ尾崎だったことにある。
ジャンボはこの2年前、1988年の東京ゴルフ倶楽部で行われた日本オープンでAON(青木功、尾崎、中嶋)三つ巴の名勝負を制し、復活をアピール。1989年の名古屋ゴルフ倶楽部和合コースでは豪州の強豪ブライアン・ジョーンズとデッドヒートの末17番、ガードバンカーからのショット1発で決めて大会2連覇。自ら「ジャンボ復活じゃない。新しい尾崎ゴルフを作り上げたんだ」とまで言い切れるほど、自信を深めていた時期だった。中嶋のみならず、誰もが3連覇の可能性を感じていた。
最終日前夜になって中嶋は、猛省する。「3日目のつまずきによって、一番大切な教えであるオールドマン・パーにたどり着いた。対戦する相手が、人からコースに変わった」。
ボビー・ジョーンズが言った、各ホールのパーを相手にプレーするスタイル。それを自らに誓って臨んだ最終日、中嶋はその通りのゴルフをした。するとどうだ。4打差が2打差まで詰まり、迎えた12番。中嶋のバーディとジャンボのボギーで、差は一気になくなった。2人は7アンダーで首位に並んだ。
残り6ホール。勝負の行方は分からなくなる。ジャンボか、中嶋か。続く2ホールで、中嶋はピンチに直面するものの驚異の粘りを見せる。特に勝負の流れを変えたのは、14番で見せた奇跡のパーセーブだった。
このホール、中嶋は第1打を大きく左に曲げて林につかまる。「木が近すぎてグリーンを狙うことは不可能だった」(中嶋)。2打目は、グリーンまで約60ヤードの所まで運ぶのが精いっぱい。350ヤードと短いパー4の14番。「ドライバー、ウェッジで乗せられるホールです。3打目を打つ前にジャンボは2オン。こっちは良くてもボギーは間違いない状況」で、中嶋は3オンしたものの、2メートルのパーパットを残した。
この2メートルが、冒頭のシーンだ。中嶋は、これをしっかり沈めてパーでしのいだ。すると、ジャンボが直後の15番から3連続ボギー。中嶋は、15番こそボギーにしたが、16、17番はパーに収めている。最終ホールは両者バーディで、中嶋7アンダー、ジャンボ5アンダーで決着がついた。
「ジャンボは、僕の3日目と一緒で、13番から人(中嶋のプレー)を見ちゃったんだと思う」。それを証明したのが、帰りの飛行機が偶然同じ便となり、またもや顔を合わせた時に、ジャンボの口をついて出た言葉だ。「お前は、魔法使いか!」(ジャンボ)。勝負どころの13、14番で神がかったようなパーセーブを連発した中嶋のプレーぶりに見入ってしまったことを告白したようなものだった。「この言葉も、うれしかったな。13、14番と奇跡的なパットを決めて、パーでしのいだことに対する言葉だったから」。中嶋はさらに、こう続けた。「“オールドマン・パー”という言葉は、ゴルファーだから誰でも知っている。でもその神髄まで(自分が)たどりつけたのは、この日の相手がジャンボだったからだと思う。他の選手が相手だったら、そこまでの心境までには至らない」。
時はまさに、AON(青木功、尾崎将司、中嶋常幸)の3強時代。振り返れば、1985年から92年までの8年間は、日本オープン優勝者はこの3人だけしかいない。「あとの2人を倒せれば、優勝できるという時代だった。この時、ジャンボは“よくやった”とたたえてくれました。うれしかったですね。こういう時、ジャンボはたたえてくれるんです。でも、青木さんは、こういう時でも、祝福してくれないの。すーっといなくなっちゃう(笑)」。
中嶋にはこの時、今も忘れられない、もう一つのうれしい出来事が起こっている。帰途の車中に直接電話が入った。受話器の向こうにいたのは、中嶋を幼少期からスパルタ教育でしごいた、父の巌氏だった。「『よくやった』とほめられたんです。後にも先にも、あれ一度きりでしたね」
それまでほめてくれたことのなかった父から贈られた、たった一度の直電メッセージだった。平成の時代に入ったばかりの日本オープン。この優勝には中嶋にとっての大切な思い出が、いくつも詰まっている。(文・小川朗)
2メートルはあったパーパットが、カップへと吸い寄せられるようにグリーンを転がっていく。真っ白なボールがカップに消えた。その瞬間、北の大地を揺るがすような大歓声が、14番グリーンを包み込んだ。
この1発が、勝負の流れをガラリと変えた。ジャンボ尾崎の日本オープン3連覇を阻んだ1打を挙げるとするならば、中嶋が入れたこのパットだということになる。
3日目を終えて中嶋はいったん、勝負をあきらめかけた。首位を明け渡した相手は、ジャンボ尾崎。最終日の18ホールを残しての4ストロークは、絶望的な差に思えたからだ。
「とにかく、あの頃のジャンボは強かったからね」(中嶋)
国内最高峰の大会である日本オープン。中嶋は初日2位の好スタートを切って、2日目に首位に立ってトーナメント前半を折り返した。しかし3日目は、どんより曇った空に抑え付けられたかのように、自分のゴルフができなかった。首位を明け渡した原因は、中嶋の内にあった。「人を見ちゃダメなんだ」。
ライバルとの闘いに身を焦がし、自ら崩れてしまった3日目の18ホール。それは日本オープンと言う大舞台ではなく、戦っている目の前の相手が、当時最強の呼び声が高かった、ジャンボ尾崎だったことにある。
ジャンボはこの2年前、1988年の東京ゴルフ倶楽部で行われた日本オープンでAON(青木功、尾崎、中嶋)三つ巴の名勝負を制し、復活をアピール。1989年の名古屋ゴルフ倶楽部和合コースでは豪州の強豪ブライアン・ジョーンズとデッドヒートの末17番、ガードバンカーからのショット1発で決めて大会2連覇。自ら「ジャンボ復活じゃない。新しい尾崎ゴルフを作り上げたんだ」とまで言い切れるほど、自信を深めていた時期だった。中嶋のみならず、誰もが3連覇の可能性を感じていた。
最終日前夜になって中嶋は、猛省する。「3日目のつまずきによって、一番大切な教えであるオールドマン・パーにたどり着いた。対戦する相手が、人からコースに変わった」。
ボビー・ジョーンズが言った、各ホールのパーを相手にプレーするスタイル。それを自らに誓って臨んだ最終日、中嶋はその通りのゴルフをした。するとどうだ。4打差が2打差まで詰まり、迎えた12番。中嶋のバーディとジャンボのボギーで、差は一気になくなった。2人は7アンダーで首位に並んだ。
残り6ホール。勝負の行方は分からなくなる。ジャンボか、中嶋か。続く2ホールで、中嶋はピンチに直面するものの驚異の粘りを見せる。特に勝負の流れを変えたのは、14番で見せた奇跡のパーセーブだった。
このホール、中嶋は第1打を大きく左に曲げて林につかまる。「木が近すぎてグリーンを狙うことは不可能だった」(中嶋)。2打目は、グリーンまで約60ヤードの所まで運ぶのが精いっぱい。350ヤードと短いパー4の14番。「ドライバー、ウェッジで乗せられるホールです。3打目を打つ前にジャンボは2オン。こっちは良くてもボギーは間違いない状況」で、中嶋は3オンしたものの、2メートルのパーパットを残した。
この2メートルが、冒頭のシーンだ。中嶋は、これをしっかり沈めてパーでしのいだ。すると、ジャンボが直後の15番から3連続ボギー。中嶋は、15番こそボギーにしたが、16、17番はパーに収めている。最終ホールは両者バーディで、中嶋7アンダー、ジャンボ5アンダーで決着がついた。
「ジャンボは、僕の3日目と一緒で、13番から人(中嶋のプレー)を見ちゃったんだと思う」。それを証明したのが、帰りの飛行機が偶然同じ便となり、またもや顔を合わせた時に、ジャンボの口をついて出た言葉だ。「お前は、魔法使いか!」(ジャンボ)。勝負どころの13、14番で神がかったようなパーセーブを連発した中嶋のプレーぶりに見入ってしまったことを告白したようなものだった。「この言葉も、うれしかったな。13、14番と奇跡的なパットを決めて、パーでしのいだことに対する言葉だったから」。中嶋はさらに、こう続けた。「“オールドマン・パー”という言葉は、ゴルファーだから誰でも知っている。でもその神髄まで(自分が)たどりつけたのは、この日の相手がジャンボだったからだと思う。他の選手が相手だったら、そこまでの心境までには至らない」。
時はまさに、AON(青木功、尾崎将司、中嶋常幸)の3強時代。振り返れば、1985年から92年までの8年間は、日本オープン優勝者はこの3人だけしかいない。「あとの2人を倒せれば、優勝できるという時代だった。この時、ジャンボは“よくやった”とたたえてくれました。うれしかったですね。こういう時、ジャンボはたたえてくれるんです。でも、青木さんは、こういう時でも、祝福してくれないの。すーっといなくなっちゃう(笑)」。
中嶋にはこの時、今も忘れられない、もう一つのうれしい出来事が起こっている。帰途の車中に直接電話が入った。受話器の向こうにいたのは、中嶋を幼少期からスパルタ教育でしごいた、父の巌氏だった。「『よくやった』とほめられたんです。後にも先にも、あれ一度きりでしたね」
それまでほめてくれたことのなかった父から贈られた、たった一度の直電メッセージだった。平成の時代に入ったばかりの日本オープン。この優勝には中嶋にとっての大切な思い出が、いくつも詰まっている。(文・小川朗)