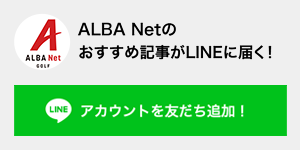第9回は1990年日本プゴルフ選手権。初めての勝利の美酒をビッグタイトルで味わった加瀬秀樹は、後に振り返ってもなぜできたのかわからない気持ちの切り替えを経験した。人生を変えた戦いを振り返る。
記録的な暑さと言われた1990年8月。第58回日本プロゴルフ選手権の舞台は、大阪・天野山カントリークラブ。加瀬は、シード選手として初めてのシーズンをプレーし、大一番に臨んでいた。
烏山城CC(栃木県)で行われた前年大会で2位になり、手にしたシード権。「台風で最終日ができるかできないか、という状況でジャンボ(尾崎将司)が勝ったんだけど、まくって2位。これが効いて、シードが取れた。日本プロはゴルフ人生を変えた試合。(1990年の)試合前に勝てるとは思ってなかったけど、縁起のいい試合だとは思っていた」。シードを手にしたのはツアー7年目の29歳の時。30歳になって迎えたシーズンは、順調だった。
「初めて」なのは、もうひとつあった。その週からメタルヘッドのドライバーを使い始めていたのだ。「まだメタルが出始めの頃で、初めて打ったのが(大会2日前の)火曜日。思うように使えたし、たぶん前より飛んでた。気持ちよくプレーできたから、いきなり試合で使った」。これも、大きな転機を支えた。
予選会から試合に出ていた前年までと違い、安心して試合に出られるシーズンは張りがある。初日は1アンダーの滑り出し。8アンダー首位の渡辺司に7打差20位だった。
優勝戦線に顔を出したのは2日目だ。6アンダー「66」でプレーしてトータル7アンダー。藤木三郎に1打差2位で決勝ラウンドに進む。3日目は皿にスコアを5つ伸ばしてトータル12アンダー。単独首位に立つ。1打差には倉本昌弘。1打遅れて藤木と、強豪が迫る激戦模様となった。
最終組でのプレーには、緊張感が伴う。「5番でOBを打ってるのよ。そこで藤木さんと並んだんだけど、逆にすごくすっきりした。焦るとかじゃなく、そこからスタートできる気がして。『ここからだな』って思えた。いい開き直り方ができた。1つのミスがいいほうに自分の感情を持って行けた」。
前年の2位は最終日にまくってのもの。優勝争いと言えるような戦いは初めてで、気持ちの持っていき方も、戦い方も知らないはずなのに、絶妙のセルフコントロールができた。「後で考えてもなぜかわからないけど、気持ちの切り替えができた」と言う不思議なターニングポイントだった。
「そこから滅茶苦茶プレーに集中できた」と、優勝へのプレシャーは感じないままホールを重ねていく。大詰めに入っても、それは変わらないままだった。「17番からは何か楽になった、と、余裕で迎えた最終ホール。最後は、チップインバーディで幕を下ろした。トータル14アンダー。藤木に5打差をつける圧勝だった。「(優勝が)決まってワーッと(歓声が上がって)ボールを投げて、なんてイメージしてたけど、入っちゃったからウイニングパットも打ってない」と、あっけなく初優勝が決まった。
ボールマークに使い、優勝を導いたコインは、名前入りの特注品。それをなくしたことに気が付いたが、テレビ中継を後から見ると、胴上げされているときに落ちたのが見えた。後日、探してもらって見つかり、手元に戻ってきたのが、ラッキーウィークの締めくくりとなった。
思い返せば、漠然とした予兆のようなものはあった。シード選手として臨んだこの年、日本プロまでの試合はすべて「前の年より成績がよかった。日本プロは前の年2位でしょ。そうすると優勝しかないかな、なんて思ってた」と笑う。
前の年の12月に30歳になったばかり。AON(青木功、尾崎将司、中嶋常幸)がどっしりとツアーの中枢に居座り、優勝争いの相手だった倉本らが脇を固める。「40歳前後が脂がのっている時期、って言われてましたね」という時代。30歳の加瀬は“若手の大型選手”という立ち位置だった。
「勝ちたい気持ちはやまやまだったけど、シードも取ったばかりだったし、ずーっと一生懸命やってるタイプだった。常にベストを尽くそうと言う気持ちはあったけどね。でも、1つ勝てたことで『自分にも勝てるんだ』という気持ちが生まれた」と、この優勝をきっかけに、加瀬は大きく大きなステップとなった初優勝だった。
シードを取り、日本プロ王者となった加瀬は、これをきっかけに飛躍していく。93年には一度、賞金シードを逃したものの、しっかりとそこからカムバック。97年には米ツアーQスクールにチャレンジした。16位で出場権を獲得し。レベルの高いフィールドでのプレーも経験している。「(米国には)アーノルド・パーマーが見たいと思って行きました。アメリカに行ったのは、やっぱり日本プロに勝ったから」。ツアーでは、4勝を挙げている。
2010年にシニア入りしてからの初優勝は、日本プロシニア。同じ日本プロゴルフ協会の公式戦との縁を感じると言う。「あれ(日本プロ優勝がなかったら、人生どうなってたかわからない」という、大きな、大きな1勝だった。(文・小川淳子)
記録的な暑さと言われた1990年8月。第58回日本プロゴルフ選手権の舞台は、大阪・天野山カントリークラブ。加瀬は、シード選手として初めてのシーズンをプレーし、大一番に臨んでいた。
烏山城CC(栃木県)で行われた前年大会で2位になり、手にしたシード権。「台風で最終日ができるかできないか、という状況でジャンボ(尾崎将司)が勝ったんだけど、まくって2位。これが効いて、シードが取れた。日本プロはゴルフ人生を変えた試合。(1990年の)試合前に勝てるとは思ってなかったけど、縁起のいい試合だとは思っていた」。シードを手にしたのはツアー7年目の29歳の時。30歳になって迎えたシーズンは、順調だった。
「初めて」なのは、もうひとつあった。その週からメタルヘッドのドライバーを使い始めていたのだ。「まだメタルが出始めの頃で、初めて打ったのが(大会2日前の)火曜日。思うように使えたし、たぶん前より飛んでた。気持ちよくプレーできたから、いきなり試合で使った」。これも、大きな転機を支えた。
予選会から試合に出ていた前年までと違い、安心して試合に出られるシーズンは張りがある。初日は1アンダーの滑り出し。8アンダー首位の渡辺司に7打差20位だった。
優勝戦線に顔を出したのは2日目だ。6アンダー「66」でプレーしてトータル7アンダー。藤木三郎に1打差2位で決勝ラウンドに進む。3日目は皿にスコアを5つ伸ばしてトータル12アンダー。単独首位に立つ。1打差には倉本昌弘。1打遅れて藤木と、強豪が迫る激戦模様となった。
最終組でのプレーには、緊張感が伴う。「5番でOBを打ってるのよ。そこで藤木さんと並んだんだけど、逆にすごくすっきりした。焦るとかじゃなく、そこからスタートできる気がして。『ここからだな』って思えた。いい開き直り方ができた。1つのミスがいいほうに自分の感情を持って行けた」。
前年の2位は最終日にまくってのもの。優勝争いと言えるような戦いは初めてで、気持ちの持っていき方も、戦い方も知らないはずなのに、絶妙のセルフコントロールができた。「後で考えてもなぜかわからないけど、気持ちの切り替えができた」と言う不思議なターニングポイントだった。
「そこから滅茶苦茶プレーに集中できた」と、優勝へのプレシャーは感じないままホールを重ねていく。大詰めに入っても、それは変わらないままだった。「17番からは何か楽になった、と、余裕で迎えた最終ホール。最後は、チップインバーディで幕を下ろした。トータル14アンダー。藤木に5打差をつける圧勝だった。「(優勝が)決まってワーッと(歓声が上がって)ボールを投げて、なんてイメージしてたけど、入っちゃったからウイニングパットも打ってない」と、あっけなく初優勝が決まった。
ボールマークに使い、優勝を導いたコインは、名前入りの特注品。それをなくしたことに気が付いたが、テレビ中継を後から見ると、胴上げされているときに落ちたのが見えた。後日、探してもらって見つかり、手元に戻ってきたのが、ラッキーウィークの締めくくりとなった。
思い返せば、漠然とした予兆のようなものはあった。シード選手として臨んだこの年、日本プロまでの試合はすべて「前の年より成績がよかった。日本プロは前の年2位でしょ。そうすると優勝しかないかな、なんて思ってた」と笑う。
前の年の12月に30歳になったばかり。AON(青木功、尾崎将司、中嶋常幸)がどっしりとツアーの中枢に居座り、優勝争いの相手だった倉本らが脇を固める。「40歳前後が脂がのっている時期、って言われてましたね」という時代。30歳の加瀬は“若手の大型選手”という立ち位置だった。
「勝ちたい気持ちはやまやまだったけど、シードも取ったばかりだったし、ずーっと一生懸命やってるタイプだった。常にベストを尽くそうと言う気持ちはあったけどね。でも、1つ勝てたことで『自分にも勝てるんだ』という気持ちが生まれた」と、この優勝をきっかけに、加瀬は大きく大きなステップとなった初優勝だった。
シードを取り、日本プロ王者となった加瀬は、これをきっかけに飛躍していく。93年には一度、賞金シードを逃したものの、しっかりとそこからカムバック。97年には米ツアーQスクールにチャレンジした。16位で出場権を獲得し。レベルの高いフィールドでのプレーも経験している。「(米国には)アーノルド・パーマーが見たいと思って行きました。アメリカに行ったのは、やっぱり日本プロに勝ったから」。ツアーでは、4勝を挙げている。
2010年にシニア入りしてからの初優勝は、日本プロシニア。同じ日本プロゴルフ協会の公式戦との縁を感じると言う。「あれ(日本プロ優勝がなかったら、人生どうなってたかわからない」という、大きな、大きな1勝だった。(文・小川淳子)