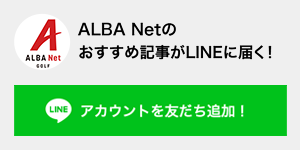今回は1995年住友VISA太平洋マスターズで見せた東聡の優勝劇を振り返る。予選ラウンドで欧米の賞金王に勝って首位に立ち、棄権を覚悟しながらの最終日を乗り越えた裏にあったものとは―。
「!!」。東聡の左肩に激痛が走ったのは、最終日の朝、スタート前の練習場でのことだった。東が、悪夢の瞬間を振り返る。「短いクラブから始めて、5番(アイアン)だったか…逆目の芝に『ガン!』と突っかかって、左の肩を痛めてしまった」。痛みは、深刻なものだった。「もう、球を打てそうもないな、となってしまった。気持ち的には、7割がた、棄権に傾いていましたから」。
とはいえ、簡単にあきらめられるような状況ではなかった。1995年11月。東は秋のビッグトーナメント、住友VISA太平洋マスターズで2位に2打差をつけ、単独のトーナメントリーダーに立っていた。しかもここまで、賞金ランキングでもトップ。春先にデサントクラシック、つるやオープンと2週連続優勝を飾り、秋口のジュンクラシックでも師匠のジャンボ尾崎、欧州の賞金王コリン・モンゴメリーを抑えて優勝と、絶好調のシーズンを送っていた。太平洋からダンロップフェニックス、カシオワールド、日本シリーズと続く高額大会の初戦をモノにするとなれば、大本命のジャンボ尾崎を抑えての賞金王も現実味を帯びる。
スタート時間が刻々と迫る中、東は導入されたばかりのフィットネストレーラーで電気治療を受ける。スタートまではもう40分しかない。痛み止めも飲んでみたが、事態は改善しない。もはや、これまでか。
次の瞬間、トレーナーから意外な言葉を投げかけられる。「とりあえず、行ってみれば?痛ければ、そこで帰ってくればいいんだし。ここでやめる必要ないんじゃない?」。その言葉に押されるように、東はトレーラーを出た。スタート時間は25分後に迫っていた。
初日、2日目とアメリカの賞金王グレッグ・ノーマンと前出のモンゴメリーとラウンド。欧米の賞金王を、日本の賞金トップの東が迎え撃つ、という重責を担いながら、堂々の首位で最終日を迎えていた。
「ノーマンを見られる一番近いギャラリーとして試合に入っていました。見ながら、あんなティショットするんだ、とかセカンドああ打つんだ、とか見ながらやっていましたね。今までにない感覚で緊張もすることなく、ドンドンスコアが積み重なっていったんです」
最終日の練習グリーンからは、徐々に選手が減っていく。最終組の3人しか、グリーン上にいなくなった。最終日ならではの光景だ。パッティングの調子はずっと良かった。ボールを転がしているうちに、スタート時間がやってきた。「7割がた棄権しようかな、という気分でした。もう今シーズン終わったかな。これも運命だな、と覚悟しました。とにかく痛かったから…。ティショット打ってみて、セカンド打って、痛かったらやめるしかないな、という気持ちでしたね」
「打てるかな?」と半信半疑でアドレスに入る。棄権覚悟でスイングするとボールは秋空に高々と舞い上がる。「意外にも打てた」ティショットに続き、第2打も問題なく振れた。
3番でバーディが先行すると、すでに痛みを忘れていた。「痛み止めが効いたのか、試合に集中して気持ちが勝ったのか…。とにかくその後は、試合に集中できていました」。15番を終えて、スタート時あった2位との2打差がキープできていた。
16番で30センチに付けるスーパーショットでバーディを奪うと、続く17番、逆さ富士が池に映る名物パー3でピンチがやって来る。「右のグラスバンカーに入ったんです。ボールは見えないほど深かったですが、幸いにして順目だった。前のホールのバーディで2位に3打差がついていたんで、仮にここでボギーにして2位の選手が18番でバーディでもまだ1打差ある、と思って打ちました」
ピンまでは約18メートル。ボールは東のイメージした通りの高さに飛び出した。「球が飛んでいる最中に『あ、これ、入ったわ』と思いました」。ボールは狙ったところに寸分の狂いもなく落ち、フックラインを描いてカップに消えた。大歓声がグリーン全体を包み込む。2位に4打差をつける、劇的なウイニングショットとなった。
最終18番、パー5の攻め方は徹底していた。「4打差になったんで、あとは余計なことはしなくて、カッコ悪いけど最低でも6(ボギー)であがれればいい。それにはティショットをOBしないこと。きれいな勝ち方をしたくなくて、左のバンカーを向いて、狙って打って入れました。フェアウエーに打って第2打が240ヤードなら狙わざるを得なくなる。スプーン(3番ウッド)でグリーンに打つことになると、何でも起こり得ますからね。バンカーから7番アイアンで打って、残り120ヤード弱の所に止めました。ここからサイドスピンがかかると池に入りますから、ピッチングウェッジでピンの左に打っていく。そういうつもりでプレーしました」
しかし3打目で色気が出た。「ピンの後ろから戻して寄せよう」と思ったのが間違いで、ボールは上の段に載ってしまった。「こうなると、完全に3パット狙い。目指していた通りの6で上がって、優勝することができました」。それでもボギーはこのひとつだけ。棄権を覚悟してスタートした最終日、崩れることなく6バーディ、1ボギーの「67」。2位の丸山茂樹に4打差をつけての見事な優勝劇だった。
優勝直後、グリーンサイドに駆けつけてくれた、師匠ジャンボの姿が目に入った。東にとって、ジャンボは小学時代からあこがれのスター。ジャンボ軍団に入ってからもその気持ちは変わらず、シニアとなった今でも目を合わせられないほど尊敬している。そのジャンボに「『おめでとう』と言ってもらえたのは、何よりもうれしかったです」
だが、この優勝で払った代償もまた大きかった。「その後はずっとこのケガを引きずりましたね。今、左肩の腱はほぼ断裂しましたから」。賞金ランクでもジャンボに逆転され2位に甘んじた。とはいえ、このシーズンの健闘が評価され、マスターズから招待状が届く。翌年東はジャンボと共に、遥かなるオーガスタの地を踏んだ。(文・小川朗)
「!!」。東聡の左肩に激痛が走ったのは、最終日の朝、スタート前の練習場でのことだった。東が、悪夢の瞬間を振り返る。「短いクラブから始めて、5番(アイアン)だったか…逆目の芝に『ガン!』と突っかかって、左の肩を痛めてしまった」。痛みは、深刻なものだった。「もう、球を打てそうもないな、となってしまった。気持ち的には、7割がた、棄権に傾いていましたから」。
とはいえ、簡単にあきらめられるような状況ではなかった。1995年11月。東は秋のビッグトーナメント、住友VISA太平洋マスターズで2位に2打差をつけ、単独のトーナメントリーダーに立っていた。しかもここまで、賞金ランキングでもトップ。春先にデサントクラシック、つるやオープンと2週連続優勝を飾り、秋口のジュンクラシックでも師匠のジャンボ尾崎、欧州の賞金王コリン・モンゴメリーを抑えて優勝と、絶好調のシーズンを送っていた。太平洋からダンロップフェニックス、カシオワールド、日本シリーズと続く高額大会の初戦をモノにするとなれば、大本命のジャンボ尾崎を抑えての賞金王も現実味を帯びる。
スタート時間が刻々と迫る中、東は導入されたばかりのフィットネストレーラーで電気治療を受ける。スタートまではもう40分しかない。痛み止めも飲んでみたが、事態は改善しない。もはや、これまでか。
次の瞬間、トレーナーから意外な言葉を投げかけられる。「とりあえず、行ってみれば?痛ければ、そこで帰ってくればいいんだし。ここでやめる必要ないんじゃない?」。その言葉に押されるように、東はトレーラーを出た。スタート時間は25分後に迫っていた。
初日、2日目とアメリカの賞金王グレッグ・ノーマンと前出のモンゴメリーとラウンド。欧米の賞金王を、日本の賞金トップの東が迎え撃つ、という重責を担いながら、堂々の首位で最終日を迎えていた。
「ノーマンを見られる一番近いギャラリーとして試合に入っていました。見ながら、あんなティショットするんだ、とかセカンドああ打つんだ、とか見ながらやっていましたね。今までにない感覚で緊張もすることなく、ドンドンスコアが積み重なっていったんです」
最終日の練習グリーンからは、徐々に選手が減っていく。最終組の3人しか、グリーン上にいなくなった。最終日ならではの光景だ。パッティングの調子はずっと良かった。ボールを転がしているうちに、スタート時間がやってきた。「7割がた棄権しようかな、という気分でした。もう今シーズン終わったかな。これも運命だな、と覚悟しました。とにかく痛かったから…。ティショット打ってみて、セカンド打って、痛かったらやめるしかないな、という気持ちでしたね」
「打てるかな?」と半信半疑でアドレスに入る。棄権覚悟でスイングするとボールは秋空に高々と舞い上がる。「意外にも打てた」ティショットに続き、第2打も問題なく振れた。
3番でバーディが先行すると、すでに痛みを忘れていた。「痛み止めが効いたのか、試合に集中して気持ちが勝ったのか…。とにかくその後は、試合に集中できていました」。15番を終えて、スタート時あった2位との2打差がキープできていた。
16番で30センチに付けるスーパーショットでバーディを奪うと、続く17番、逆さ富士が池に映る名物パー3でピンチがやって来る。「右のグラスバンカーに入ったんです。ボールは見えないほど深かったですが、幸いにして順目だった。前のホールのバーディで2位に3打差がついていたんで、仮にここでボギーにして2位の選手が18番でバーディでもまだ1打差ある、と思って打ちました」
ピンまでは約18メートル。ボールは東のイメージした通りの高さに飛び出した。「球が飛んでいる最中に『あ、これ、入ったわ』と思いました」。ボールは狙ったところに寸分の狂いもなく落ち、フックラインを描いてカップに消えた。大歓声がグリーン全体を包み込む。2位に4打差をつける、劇的なウイニングショットとなった。
最終18番、パー5の攻め方は徹底していた。「4打差になったんで、あとは余計なことはしなくて、カッコ悪いけど最低でも6(ボギー)であがれればいい。それにはティショットをOBしないこと。きれいな勝ち方をしたくなくて、左のバンカーを向いて、狙って打って入れました。フェアウエーに打って第2打が240ヤードなら狙わざるを得なくなる。スプーン(3番ウッド)でグリーンに打つことになると、何でも起こり得ますからね。バンカーから7番アイアンで打って、残り120ヤード弱の所に止めました。ここからサイドスピンがかかると池に入りますから、ピッチングウェッジでピンの左に打っていく。そういうつもりでプレーしました」
しかし3打目で色気が出た。「ピンの後ろから戻して寄せよう」と思ったのが間違いで、ボールは上の段に載ってしまった。「こうなると、完全に3パット狙い。目指していた通りの6で上がって、優勝することができました」。それでもボギーはこのひとつだけ。棄権を覚悟してスタートした最終日、崩れることなく6バーディ、1ボギーの「67」。2位の丸山茂樹に4打差をつけての見事な優勝劇だった。
優勝直後、グリーンサイドに駆けつけてくれた、師匠ジャンボの姿が目に入った。東にとって、ジャンボは小学時代からあこがれのスター。ジャンボ軍団に入ってからもその気持ちは変わらず、シニアとなった今でも目を合わせられないほど尊敬している。そのジャンボに「『おめでとう』と言ってもらえたのは、何よりもうれしかったです」
だが、この優勝で払った代償もまた大きかった。「その後はずっとこのケガを引きずりましたね。今、左肩の腱はほぼ断裂しましたから」。賞金ランクでもジャンボに逆転され2位に甘んじた。とはいえ、このシーズンの健闘が評価され、マスターズから招待状が届く。翌年東はジャンボと共に、遥かなるオーガスタの地を踏んだ。(文・小川朗)