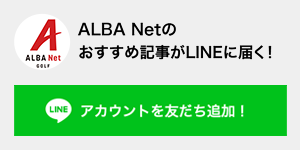歴史の重みがドラマを生む。1992年のブリヂストンオープンは、まさにそんな展開だった。大会3日目、主役の座に躍り出たのは弱冠24歳の西川哲。前年のマルマンオープンでツアー初Vを飾っており、爆発力には定評があった。
3日目の猛チャージは、その定評を証明するもの。雨が降る中、10番からの4連続バーディを含めた9バーディ、1ボギーの「64」をマーク。トータル16アンダーまで一気にスコアを伸ばし、2位の尾崎直道に2打差をつけ、首位で最終日を迎えることとなった。
最終日、その西川を猛追したのがプロ12年目、37歳と円熟の域に入りつつある倉本昌弘だった。倉本はこの年の5月中旬、下秋間CC(群馬)で行われた日本プロゴルフ選手権で中嶋常幸をプレーオフのすえ破り、同大会2勝目。通算勝利数を24に伸ばし、25勝で与えられる永久シードにも王手をかけていた。
首位に5打差でスタートした倉本はすでに2度、この大会を制していた。1984年の大会では最終日に「65」で回った岩下吉久、英国のサム・トーランス、台湾の陳志忠と4人プレーオフとなったが、1ホール目でトーランスと岩下がともに第2打を池に入れて脱落。2オンした陳との一騎打ちとなったが、1パットで沈めた倉本が通算13勝目を飾った。
翌85年は最終日の12番でトップに立った青木功との差を、16、17番のバーディで1打差まで詰めた。青木は最終18番で第2打を大きくプッシュアウト。グリーン右手前の池の、さらに右まで打ってしまう。一方の倉本は第2打をグリーン左手前のエッジまで運んでおり、楽々と寄せてOKバーディ。一方の青木はこのホールをまさかのボギーにしてしまい、倉本が大逆転で大会2連覇を達成した。
旧袖(袖ヶ浦カントリークラブ袖ヶ浦コース)に強い倉本、というイメージはすでに1980年代の半ばには定着していた。倉本は旧袖の特徴をこう語る。
「このコースは、1番は距離のあるパー4で左がダメ。2番は右のバンカーを越えていくパー5。5番までになんとかアンダーパーにできると、最終的にいいスコアを出しやすいコース。あとは風次第でコースの性格が大分変わる。1番、10番がフォローだと9番、18番がアゲンストになって難しくなる。逆に1番10番がアゲンストになって長いホールになると、逆に9、18番がフォローになる。グリーンはコーライで硬いから、グリーンに止められる選手に有利なコース」
ビッグスコアを出すコツは、5番までのスコアメークが肝心。袖ヶ浦の特性を知り尽くしているからこそ、92年最終日の「66」が可能になったわけだ。トータル17アンダーまでスコアを伸ばしてホールアウトした時には、まだ後続の組の多くがプレー中。倉本は用具契約を結んでいるブリヂストンの石橋幹一郎会長にあいさつするため18番ホールのVIP席を訪れる。流れのままに同席し、選手のプロフィールや18番の攻略法などを解説していた。
結局倉本はトップの西川が18番グリーンに上がって来るまで石橋会長と談笑していたのだが…。この後、状況が激変する。西川の第3打はグリーンこそとらえたものの、上からの長いパットを残してしまった。しかもファーストパットを大きくショート。このパットが決められないと、倉本とのプレーオフという状況となった。
当時の心境を、倉本はこう振り返った。「まさかプレーオフになるとは思っていなかったので、驚きましたね。ファーストパットがショートしたので、石橋会長には「プレーオフになるかもしれません」とあいさつして、その場を離れた。ほぼ同じころ、西川はパーパットを決められずボギー。プレーオフに突入した。
予想外の展開で、優勝のチャンスが転がり込んできた倉本と、単独首位から転落した西川のプレーオフ。1ホール目はともにパー。再度18番で行われた2ホール目、第2打を先に打った西川が池ポチャ。倉本は約250ヤードの第2打を5Wで見事2オン。2パットのバーディで、見事大会3勝目。通算25勝となり、尾崎将司、青木、中嶋、杉原輝雄に続く史上5人目となる永久シード選手の仲間入りを果たした。
経験豊富な倉本が、若い西川を相手に横綱相撲で押し切った感じの名勝負。西川とは「その後『何やってんだよ、花を持たしてくれなくてもいいのに』なんて冗談をいいつつ、食事をする仲にはなりましたね」。
表彰式のプレゼンターは、プレーオフ直前まで同席していた石橋会長。この優勝で翌年のワールドシリーズ(米オハイオ州アクロン・ファイアストーンCC)の出場権も手にした。
永久シードを獲得し、日本の出場権の心配がなくなった倉本はこの年のオフ、米ツアーのクオリファイイングスクールに挑戦し、日本人初のトップ合格。米ツアーに軸足を移して戦うことになる。当時、倉本は日本の選手会長としての使命も抱えていた。
そのためツアーを転戦中にPGAツアーの役員たちともパイプを作り、日本の男子ツアーにも米ツアーのノウハウを逆輸入するようになる。その後PGAから分離独立し、現在のJGTO設立にも重要な役割を果たすことになる倉本にとって、この優勝がのちの人生を方向付ける、節目の25勝目にもなった。(文・小川朗)
3日目の猛チャージは、その定評を証明するもの。雨が降る中、10番からの4連続バーディを含めた9バーディ、1ボギーの「64」をマーク。トータル16アンダーまで一気にスコアを伸ばし、2位の尾崎直道に2打差をつけ、首位で最終日を迎えることとなった。
最終日、その西川を猛追したのがプロ12年目、37歳と円熟の域に入りつつある倉本昌弘だった。倉本はこの年の5月中旬、下秋間CC(群馬)で行われた日本プロゴルフ選手権で中嶋常幸をプレーオフのすえ破り、同大会2勝目。通算勝利数を24に伸ばし、25勝で与えられる永久シードにも王手をかけていた。
首位に5打差でスタートした倉本はすでに2度、この大会を制していた。1984年の大会では最終日に「65」で回った岩下吉久、英国のサム・トーランス、台湾の陳志忠と4人プレーオフとなったが、1ホール目でトーランスと岩下がともに第2打を池に入れて脱落。2オンした陳との一騎打ちとなったが、1パットで沈めた倉本が通算13勝目を飾った。
翌85年は最終日の12番でトップに立った青木功との差を、16、17番のバーディで1打差まで詰めた。青木は最終18番で第2打を大きくプッシュアウト。グリーン右手前の池の、さらに右まで打ってしまう。一方の倉本は第2打をグリーン左手前のエッジまで運んでおり、楽々と寄せてOKバーディ。一方の青木はこのホールをまさかのボギーにしてしまい、倉本が大逆転で大会2連覇を達成した。
旧袖(袖ヶ浦カントリークラブ袖ヶ浦コース)に強い倉本、というイメージはすでに1980年代の半ばには定着していた。倉本は旧袖の特徴をこう語る。
「このコースは、1番は距離のあるパー4で左がダメ。2番は右のバンカーを越えていくパー5。5番までになんとかアンダーパーにできると、最終的にいいスコアを出しやすいコース。あとは風次第でコースの性格が大分変わる。1番、10番がフォローだと9番、18番がアゲンストになって難しくなる。逆に1番10番がアゲンストになって長いホールになると、逆に9、18番がフォローになる。グリーンはコーライで硬いから、グリーンに止められる選手に有利なコース」
ビッグスコアを出すコツは、5番までのスコアメークが肝心。袖ヶ浦の特性を知り尽くしているからこそ、92年最終日の「66」が可能になったわけだ。トータル17アンダーまでスコアを伸ばしてホールアウトした時には、まだ後続の組の多くがプレー中。倉本は用具契約を結んでいるブリヂストンの石橋幹一郎会長にあいさつするため18番ホールのVIP席を訪れる。流れのままに同席し、選手のプロフィールや18番の攻略法などを解説していた。
結局倉本はトップの西川が18番グリーンに上がって来るまで石橋会長と談笑していたのだが…。この後、状況が激変する。西川の第3打はグリーンこそとらえたものの、上からの長いパットを残してしまった。しかもファーストパットを大きくショート。このパットが決められないと、倉本とのプレーオフという状況となった。
当時の心境を、倉本はこう振り返った。「まさかプレーオフになるとは思っていなかったので、驚きましたね。ファーストパットがショートしたので、石橋会長には「プレーオフになるかもしれません」とあいさつして、その場を離れた。ほぼ同じころ、西川はパーパットを決められずボギー。プレーオフに突入した。
予想外の展開で、優勝のチャンスが転がり込んできた倉本と、単独首位から転落した西川のプレーオフ。1ホール目はともにパー。再度18番で行われた2ホール目、第2打を先に打った西川が池ポチャ。倉本は約250ヤードの第2打を5Wで見事2オン。2パットのバーディで、見事大会3勝目。通算25勝となり、尾崎将司、青木、中嶋、杉原輝雄に続く史上5人目となる永久シード選手の仲間入りを果たした。
経験豊富な倉本が、若い西川を相手に横綱相撲で押し切った感じの名勝負。西川とは「その後『何やってんだよ、花を持たしてくれなくてもいいのに』なんて冗談をいいつつ、食事をする仲にはなりましたね」。
表彰式のプレゼンターは、プレーオフ直前まで同席していた石橋会長。この優勝で翌年のワールドシリーズ(米オハイオ州アクロン・ファイアストーンCC)の出場権も手にした。
永久シードを獲得し、日本の出場権の心配がなくなった倉本はこの年のオフ、米ツアーのクオリファイイングスクールに挑戦し、日本人初のトップ合格。米ツアーに軸足を移して戦うことになる。当時、倉本は日本の選手会長としての使命も抱えていた。
そのためツアーを転戦中にPGAツアーの役員たちともパイプを作り、日本の男子ツアーにも米ツアーのノウハウを逆輸入するようになる。その後PGAから分離独立し、現在のJGTO設立にも重要な役割を果たすことになる倉本にとって、この優勝がのちの人生を方向付ける、節目の25勝目にもなった。(文・小川朗)