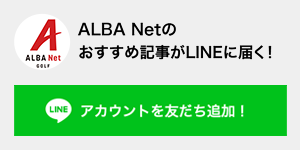海老原清治を悪夢のような出来事が襲ったのは、1985年の3月22日。期待に胸を膨らませて臨んだ開幕戦、静岡オープン(静岡CC浜岡C)の試合中だった。
「アイアンで打った時に(ボールの下の)木の根を打っちゃって、左の手首が外れちゃった」。
プロゴルファーにとっては命ともいえる左手首の脱臼というアクシデントともに予選落ち。病院で外れた手首を「はめてもらった」が、患部を石膏で固められ戦線離脱を余儀なくされた。
海老原にとって、勝負のシーズンだった。1970年にプロ入り後、15年目にして賞金ランク24位に入り初シードを獲得。晴れて臨んだシード1年目の出鼻を、いきなりくじかれてしまった。
復帰は3週間後の4月11日。担当の医師からは「いきなり試合じゃ大変だから、練習してから出れば?」とストップをかけられたが「いや先生、練習だと何百発も打っちゃうから、かえって手首に良くない。試合なら80くらいでは回れるだろうし、試合感覚の戻りも早いから行かせてほしい」と説得。「なるほどな、そういう考えがあるのなら、いいよ、やってみれば」とようやく許しを得て、ポカリスエットオープン(広島・白竜湖CC)から復帰した。
しかし故障のハンディは大きく、翌週のブリヂストン阿蘇(熊本・阿蘇GC)、さらに翌週のダンロップ国際オープン(茨城CC西C)とすべて予選落ち。賞金ゼロという厳しい状況が続いた。
4試合連続予選落ちという暗いトンネルの中を走り続けるうち、光が見えてきたのが5戦目となった中日クラウンズ(愛知・名古屋GC和合C)。このコースはアウト、インともパー35。海老原は初日のハーフでパープレーの「35」で回り、ようやく復活の足掛かりをつかむ。すると後半のハーフも「35」にまとめ、首位に5打差の18位で初日を終えることができた。
さらに2日目もこれまた前半、後半とも1バーディ、1ボギーの「35」でラウンドし、トータルイーブンパーの12位に浮上。シーズン初の予選通過を成し遂げた。中日クラウンズは1960年にスタートした日本最古のスポンサートーナメント。春の大一番にふさわしく賞金総額8000万円、優勝賞金1500万円と、当時の国内トーナメントではダンロップフェニックスに次ぐ高額賞金が用意されていた。
しかし当の海老原はそんな賞金には目もくれず、ただただ、予選2日間のハーフをすべてパープレーで終えられたことの喜びに浸っていた。
「予選を通れば万々歳だった。それにハーフ4つともオーバーパーを叩かず、35で回れたことがうれしかった」。
3日目は自らもびっくりのビッグスコアがやってくる。出足の1番で幸先の良いバーディを奪うと、快進撃が始まった。6バーディ2ボギーの「66」をマークして、一気に2打差の2位まで急浮上だ。
海老原は、この時の心境を、こう振り返る。「『へ〜、66も出ちゃうんだ』という感じ」と半ば他人事のようにとらえていた。しかもトップに座り最終日最終組を一緒に回るのは、当時最強の域に達していた中嶋常幸(当時は中島)。「あの頃の中嶋プロと言えばとにかく強かったから、勝てるなんてまったく思ってないよね」と、まったくの無欲で最終18ホールへと突入していく。
海老原は出足の1、2番で連続バーディ。その後2つのボギーを叩くがアウトを「35」で折り返す。9ホール単位でプレーを組み立てる海老原の感覚では“ハーフを7回連続でオーバーパーしていない"ということになる。
トータル4アンダー。前半で1オーバーの首位・中嶋との差は、わずか1ストロークまで詰まっていた。しかし当の海老原は、優勝争いの真っただ中にいるのにも関わらず「残りのハーフも、何とかパープレー以下で回りたいな」と自分のスコアのみに集中していた。
中嶋はバックナインに入ってすぐに、10番でボギー。ついに海老原と並んでしまう。この後海老原は、中嶋からいつもと違うムードを感じ取っていた。
「11番に行った時、中嶋選手がなんとなく焦っているように見えた。何でだろう。俺なんかを相手に焦っているのかな、と思いながら、プレーしていました」。
その11番で、海老原は上から5メートルのバーディパットを決めてついに逆転。しかし続く12番でボギーが出て再び並ぶ。その直後、11番で中嶋を見て抱いた違和感が、さらに明確なものとなる。一緒に回っていた矢部昭が「清ちゃん(海老原のこと)、頑張れば、チャンスあるよ。今日の中嶋選手、なんとなく普通じゃない。いつもと違うから、何とかなるかもよ」と話しかけてきたのだ。矢部は3歳上で1982年の日本オープンチャンピオン。だがこの日は10番から3連続ボギーを叩き、圏外へと後退。「途中で清ちゃんの応援団になっちゃったな」と苦笑しながらの言葉だった。
「そういえば…」無欲の海老原に、我孫子中学の先輩・青木功がかけた言葉がよみがえってきた。「清治、チャンスはあるんだから、頑張って来いよ」。
ここから、海老原にとって本当の試練がやってきた、13番のパー3では左に大きく曲げる絶体絶命のピンチ。アプローチも2メートルオーバーし、ボギーを覚悟したが「フックライン(のパーパット)が入った」。
この後も、綱渡りのゴルフが続くことになる。距離が長く、左のOBが浅い難所の14番パー4も「左だけに気を遣って右に打って、4番アイアンでセカンドを打って、よし、切り抜けた、と思った」。左ドッグレッグの16番は、入れてはいけないグリーン奥のバンカーに「9番アイアンでオーバーして入れてしまった」。それでも「このバンカーじゃどうしようもない」と思いながら放ったショットはピン2メートルにつき「このフックラインも入った」。
しのぎにしのぐ海老原とは対照的に、中嶋は14、16番とボギー。首位の座を明け渡したまま終盤を迎えてしまう。一方、海老原には大詰めの17番、名物のパー3で絶好のチャンスがやってくる。ティショットは1メートルにピタリとついた。しかしこの絶好のチャンスを、海老原は外し1メートルもオーバーしてしまう。
「こんなもの刻んでおけばいいのに、馬鹿だな俺も」と悔やみながらもこの返しを入れて首位をキープ。「18番は右にOBがあるから、左の傾斜へ低い球で打てれば、傾斜で戻ってくる」と念じながら放ったティショットは思い通りの弾道を描いてフェアウェイの左に止まる。ここからグリーンに「乗った時点でほっとしました」。13メートルのロングパットは絶妙なタッチで5センチに。中島に2打差をつけての逆転ドラマにピリオドが打たれた。
左手首の脱臼から4週連続予選落ちの末、初日から8回のハーフすべてでオーバーパーなしの完ぺきなゴルフでビッグタイトルの制覇。「それまで、自分の方が焦ってゴルフをしていたのに、あの時は中嶋選手が焦っているように見えるほど、自分が落ち着いてゴルフができていた。ゴルフができるだけでうれしくて、そもそも勝てるなんて思っていなかったんだから」。
それから、笑いながらこう続けた。「予選通って3日目66も出て最終組で回れるだけで最高だった。最後のハーフもパープレーで回れれば、ということしか考えなかった。4試合続けて予選落ちしてましたから、(決勝ラウンドを)プレー出来ているだけで『やった、やった」と思いでしたから。『ようし、やってやる』なんて思っていたら、メタメタにやられていたんじゃないですか(笑)」。(日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川朗)
「アイアンで打った時に(ボールの下の)木の根を打っちゃって、左の手首が外れちゃった」。
プロゴルファーにとっては命ともいえる左手首の脱臼というアクシデントともに予選落ち。病院で外れた手首を「はめてもらった」が、患部を石膏で固められ戦線離脱を余儀なくされた。
海老原にとって、勝負のシーズンだった。1970年にプロ入り後、15年目にして賞金ランク24位に入り初シードを獲得。晴れて臨んだシード1年目の出鼻を、いきなりくじかれてしまった。
復帰は3週間後の4月11日。担当の医師からは「いきなり試合じゃ大変だから、練習してから出れば?」とストップをかけられたが「いや先生、練習だと何百発も打っちゃうから、かえって手首に良くない。試合なら80くらいでは回れるだろうし、試合感覚の戻りも早いから行かせてほしい」と説得。「なるほどな、そういう考えがあるのなら、いいよ、やってみれば」とようやく許しを得て、ポカリスエットオープン(広島・白竜湖CC)から復帰した。
しかし故障のハンディは大きく、翌週のブリヂストン阿蘇(熊本・阿蘇GC)、さらに翌週のダンロップ国際オープン(茨城CC西C)とすべて予選落ち。賞金ゼロという厳しい状況が続いた。
4試合連続予選落ちという暗いトンネルの中を走り続けるうち、光が見えてきたのが5戦目となった中日クラウンズ(愛知・名古屋GC和合C)。このコースはアウト、インともパー35。海老原は初日のハーフでパープレーの「35」で回り、ようやく復活の足掛かりをつかむ。すると後半のハーフも「35」にまとめ、首位に5打差の18位で初日を終えることができた。
さらに2日目もこれまた前半、後半とも1バーディ、1ボギーの「35」でラウンドし、トータルイーブンパーの12位に浮上。シーズン初の予選通過を成し遂げた。中日クラウンズは1960年にスタートした日本最古のスポンサートーナメント。春の大一番にふさわしく賞金総額8000万円、優勝賞金1500万円と、当時の国内トーナメントではダンロップフェニックスに次ぐ高額賞金が用意されていた。
しかし当の海老原はそんな賞金には目もくれず、ただただ、予選2日間のハーフをすべてパープレーで終えられたことの喜びに浸っていた。
「予選を通れば万々歳だった。それにハーフ4つともオーバーパーを叩かず、35で回れたことがうれしかった」。
3日目は自らもびっくりのビッグスコアがやってくる。出足の1番で幸先の良いバーディを奪うと、快進撃が始まった。6バーディ2ボギーの「66」をマークして、一気に2打差の2位まで急浮上だ。
海老原は、この時の心境を、こう振り返る。「『へ〜、66も出ちゃうんだ』という感じ」と半ば他人事のようにとらえていた。しかもトップに座り最終日最終組を一緒に回るのは、当時最強の域に達していた中嶋常幸(当時は中島)。「あの頃の中嶋プロと言えばとにかく強かったから、勝てるなんてまったく思ってないよね」と、まったくの無欲で最終18ホールへと突入していく。
海老原は出足の1、2番で連続バーディ。その後2つのボギーを叩くがアウトを「35」で折り返す。9ホール単位でプレーを組み立てる海老原の感覚では“ハーフを7回連続でオーバーパーしていない"ということになる。
トータル4アンダー。前半で1オーバーの首位・中嶋との差は、わずか1ストロークまで詰まっていた。しかし当の海老原は、優勝争いの真っただ中にいるのにも関わらず「残りのハーフも、何とかパープレー以下で回りたいな」と自分のスコアのみに集中していた。
中嶋はバックナインに入ってすぐに、10番でボギー。ついに海老原と並んでしまう。この後海老原は、中嶋からいつもと違うムードを感じ取っていた。
「11番に行った時、中嶋選手がなんとなく焦っているように見えた。何でだろう。俺なんかを相手に焦っているのかな、と思いながら、プレーしていました」。
その11番で、海老原は上から5メートルのバーディパットを決めてついに逆転。しかし続く12番でボギーが出て再び並ぶ。その直後、11番で中嶋を見て抱いた違和感が、さらに明確なものとなる。一緒に回っていた矢部昭が「清ちゃん(海老原のこと)、頑張れば、チャンスあるよ。今日の中嶋選手、なんとなく普通じゃない。いつもと違うから、何とかなるかもよ」と話しかけてきたのだ。矢部は3歳上で1982年の日本オープンチャンピオン。だがこの日は10番から3連続ボギーを叩き、圏外へと後退。「途中で清ちゃんの応援団になっちゃったな」と苦笑しながらの言葉だった。
「そういえば…」無欲の海老原に、我孫子中学の先輩・青木功がかけた言葉がよみがえってきた。「清治、チャンスはあるんだから、頑張って来いよ」。
ここから、海老原にとって本当の試練がやってきた、13番のパー3では左に大きく曲げる絶体絶命のピンチ。アプローチも2メートルオーバーし、ボギーを覚悟したが「フックライン(のパーパット)が入った」。
この後も、綱渡りのゴルフが続くことになる。距離が長く、左のOBが浅い難所の14番パー4も「左だけに気を遣って右に打って、4番アイアンでセカンドを打って、よし、切り抜けた、と思った」。左ドッグレッグの16番は、入れてはいけないグリーン奥のバンカーに「9番アイアンでオーバーして入れてしまった」。それでも「このバンカーじゃどうしようもない」と思いながら放ったショットはピン2メートルにつき「このフックラインも入った」。
しのぎにしのぐ海老原とは対照的に、中嶋は14、16番とボギー。首位の座を明け渡したまま終盤を迎えてしまう。一方、海老原には大詰めの17番、名物のパー3で絶好のチャンスがやってくる。ティショットは1メートルにピタリとついた。しかしこの絶好のチャンスを、海老原は外し1メートルもオーバーしてしまう。
「こんなもの刻んでおけばいいのに、馬鹿だな俺も」と悔やみながらもこの返しを入れて首位をキープ。「18番は右にOBがあるから、左の傾斜へ低い球で打てれば、傾斜で戻ってくる」と念じながら放ったティショットは思い通りの弾道を描いてフェアウェイの左に止まる。ここからグリーンに「乗った時点でほっとしました」。13メートルのロングパットは絶妙なタッチで5センチに。中島に2打差をつけての逆転ドラマにピリオドが打たれた。
左手首の脱臼から4週連続予選落ちの末、初日から8回のハーフすべてでオーバーパーなしの完ぺきなゴルフでビッグタイトルの制覇。「それまで、自分の方が焦ってゴルフをしていたのに、あの時は中嶋選手が焦っているように見えるほど、自分が落ち着いてゴルフができていた。ゴルフができるだけでうれしくて、そもそも勝てるなんて思っていなかったんだから」。
それから、笑いながらこう続けた。「予選通って3日目66も出て最終組で回れるだけで最高だった。最後のハーフもパープレーで回れれば、ということしか考えなかった。4試合続けて予選落ちしてましたから、(決勝ラウンドを)プレー出来ているだけで『やった、やった」と思いでしたから。『ようし、やってやる』なんて思っていたら、メタメタにやられていたんじゃないですか(笑)」。(日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川朗)