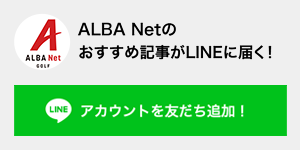今回は23歳時にマスターズと全英で屈辱にまみれた中嶋(当時は中島)常幸が、31歳にして両メジャーで優勝争いを演じるまで。
オーガスタナショナルGC13番パー5。今も語り継がれる「13」の大叩きが生まれたのは、1978年のマスターズ2日目、金曜日のことだった。中嶋はこう回想する。
「ティショットを左に引っかけた。フックしたボールが木に当たり、クリークに入った。ドロップして3打目を打った後、4打目は残り90ヤード。ピンは手前だったね。このショットが弱くてまたクリークの中へ。でも打てそうだった。だから5打目を打ったけど、これが自分の体に当たって2ペナルティー。我を忘れて(ハザード内の)地面を叩いてまた2ペナルティー(笑い)。打ち直しの11打目をグリーン奥に打って2パット」。我を忘れる事態だっただけに、スコアの計算もおぼつかない。「同伴プレーヤーと15番のフェアウェイまで数えていて、ようやく『13』で落ち着いた」(中嶋)
初日の「80」に続き、2日目も80。中嶋のマスターズ初挑戦は、13番でのワースト記録とともに、ショッキングな結果に終わった。当時、傷心の中嶋は「一刻も早くオーガスタを離れたい」と語り同行した加納徹也氏(ゴルフリポーター)とともにアトランタ空港まで車を走らせ、一夜を明かすことになる。「勉強のために残る、というのは許されない雰囲気でもあったよね。親父(父・巌氏=故人)から早く帰って来いと言われたし」。
中嶋はオーガスタに足を踏み入れた時から、大きなショックに見舞われていた。「親父の元でやって来て、夢にまで見たマスターズに出られた。でも実際に行ってみると衝撃だった」。練習場で目の当たりにした世界のレベルの高さに圧倒されてしまった。
「選手たちは150ヤードから250ヤードまでの落下地点にキャディを立たせて、当たり前のように打っていた。正確無比で精度とパワーが圧倒的に違う。自分は短いクラブはできるけど、長いクラブになるとボールはあちこちに散らばるから恥ずかしくて、みんながいないところでしか練習できなかった」。
中島にとって、初めてのマスターズを戦うまでに経験した海外の試合は、前年11月にフロリダで開催されたダブルス戦と、マスターズ前の2月にペブルビーチなどで開催されたビング・クロスビープロアマの2試合のみ。経験の浅さが、大叩きの原因となっていたのは明らかだった。
帰国すると不屈の闘志で再起し、課題に取り組むこととなる。それは4か月後、聖地セントアンドリュースで行われた全英オープンで早くも実を結びかけた。中嶋は3日目の16番を終えてトップタイの大健闘を演じるまでになっていた。ところがここでまた、悪夢のような出来事が起こった。
鉄道跡の道(ロード)が走り、右サイドのオールドコースホテルの敷地に向かって打って行く通称ロードホールの17番。中嶋は手堅く2オンを果たしたが、ギャラリーはここから驚きの光景を目にすることになる。
再び中嶋の回想。「一緒に回っていたのはトム・ワイスコフ。2段グリーンの右手前に乗ったんだけど、上の段のピンまで20メートルくらいあった。2段グリーンを斜めに上がっていかなければいけないファーストパットは当たりそこないで、手前で左に曲がりグリーンを出て、バンカーに入ってしまった。『嘘だろ』という思いだった」。4打目となるバンカーショットはいったん脱出するものの、グリーン手前の傾斜に止まってからゆっくりとバンカーへと戻ってくる。5打目も同じようにバンカーへと戻り、6打目も…。結局7打目でようやくピンの奥に止まったが、2パットの「9」を叩いてしまう。
バンカー内で4打を叩いての「9」も伝説となり、ロードバンカーは別名「トミーズ・バンカー」とも呼ばれるようになった。23歳でオーガスタナショナル、セントアンドリュースという名コースで受けたあまりに過酷な試練を、中嶋はどう受け止めていたのか。
「その晩はホテルに帰って、ベッドを思い切り蹴り上げるほど、情けなくて悔しかった。でも13を叩いたマスターズからわずか4カ月後の全英で、予選から行って、出られて、優勝争いまでできたんだよ。努力が早くも開花したことで、『意外と世界は近いじゃん』と思えたのも事実。優勝争いからは脱落したけど、最終日にあこがれのアーノルド・パーマーと回れたことは大きかった。パーマーは特別な存在だったんだ。後にも先にも、サインをもらったのはこの時のパーマーだけだから。いいかと思っていたら17番で叩かれて、へこんで意気消沈してたけど、パーマーに救われた感じだった。パーマーの前でいい加減なゴルフはできないしね」
このメジャー2試合の経験で、課題も明確になった。「結局のところ、経験不足が原因なのよ。セントアンドリュースの3打目のファーストパットも、本人はピタッとつけるもんだと思っている。でも経験を積んでくれば、あれは1ピン程度によればいいと割り切れるから、間違ってもファーストパットをバンカーに入れてしまうなんてことは起こりえない。“足る”を知らないわけよ」。
それから8年――。中嶋は多くの経験を積んで、オーガスタでもその実力をいかんなく発揮するようになる。特に1986年のマスターズは、最も優勝に近づいた試合だった。
初日は2アンダーの「70」で回り、首位のビル・クラッツアートとケン・グリーンに2打差の5位でスタートした。2日目は通算5アンダーで首位に立ったセベ・バレステロスから2打差の3位。そして3日目は、通算6アンダーで首位に立ったグレッグ・ノーマンに、やはり2打差の6位タイで最終日を迎えた。
最終日の前半9ホールを終えて、中嶋は1オーバーの37。トム・ワトソンと同じ3アンダーでサンデーバックナインに突入した。首位をいくジャック・ニクラウスとノーマンとは、ここで2打差とあって、勝機は十分にあった。
しかし中嶋は、ここでオーガスタが持つ本当の怖さを実感することになる。結局バックナインは35に終わり、優勝したニクラウスからは5打遅れての8位フィニッシュ。「オーガスタのサンデーバックナインの厳しさを実感した。そこは本当に苦しかった。それを知っているだけに、松山(英樹)がバックナインを抜けてきた時に(実況席で)涙をこらえきれなかったんだ」と中嶋はしみじみとした口調で振り返った。
とはいえだ。23歳の時には初日、2日目と80を叩き、全く歯が立たなかった中嶋が、31歳となり大きく成長したことを、この年、オーガスタのパトロンたちに証明して見せた。
さらに4か月後。ターンベリーで行われた「全英オープン」でも、初日こそ4オーバーの「74」を叩き出遅れたものの、2日目に「67」をマークして首位のノーマンから4打差に迫る。3日目も「71」で踏ん張り、首位のノーマンに1打差の2位に浮上。全英オープンの大舞台で、最終日最終組をラウンドすることになったのだ。
しかしここでも、勝利の女神は中嶋に微笑まなかった。「自分のミスで負けた。自滅で崩れた」(中嶋)最終日は77を叩き、結局マスターズと同じく8位タイに終わり、優勝したノーマンを祝福する立場となってしまった。囲み取材では人目もはばからず、号泣することになる。「松山も(2017年の)全米プロゴルフ選手権でジャスティン・トーマスに負けて号泣したよね。同じ自滅の形だっただけに、あのシーンも(自分に)ダブるんだよ」。
この後、中嶋は律子夫人とともに、重い足取りでホテルの階段を上っていく。その時、自分に向けてバグパイプの演奏が行われているのに気づく。「200人ぐらいの宿泊客が、我々に向かって拍手を送ってくれていた。後ろを振り返っても、誰もいない。敗者に対する思いやりだと、その時分かった。勝者だけじゃなく、敗者も大事なんだ、という気持ちが伝わってきたよね」。
かつてオールドコースのバンカーで4度も叩き、トップタイの座から転落していった23歳の若者が、31歳になって優勝争いをしたことを、スコットランドの多くのファンが知っていた。健闘をねぎらう拍手と歓声が、中嶋夫妻を優しく包んでいた。
メジャー挑戦の歴史を振り返り、中嶋が言う。「やっぱり今の自分を作ってくれたのは、13を叩いたマスターズ。あそこが原点です。あの後、2通りのパターンがあったと思う。もう世界をあきらめるか、もう一度世界を知った上で目指すのか。幸いにして自分は後者になれたよね。親父が課題を出してくれたこともあって、世界の現実を練習に生かして、自分を変えなきゃいけない、と思えた。それが1986年のマスターズと全英での優勝争いにつながったのだと思う。負けたままで終わらなかったのは…。歩みを止めないことが大切なんだと思うよ」。
いかなるショックに見舞われても、挑戦を続けること。そこで得た苦い経験も、知識とともに自分の中に取り込んでいく。そのことの大切さを、優勝には手が届かないながらも中嶋はメジャーの舞台において優勝争いをすることで証明した。いずれも、中嶋常幸の血肉となった名勝負だったのは間違いない。(取材・構成=日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川朗)
オーガスタナショナルGC13番パー5。今も語り継がれる「13」の大叩きが生まれたのは、1978年のマスターズ2日目、金曜日のことだった。中嶋はこう回想する。
「ティショットを左に引っかけた。フックしたボールが木に当たり、クリークに入った。ドロップして3打目を打った後、4打目は残り90ヤード。ピンは手前だったね。このショットが弱くてまたクリークの中へ。でも打てそうだった。だから5打目を打ったけど、これが自分の体に当たって2ペナルティー。我を忘れて(ハザード内の)地面を叩いてまた2ペナルティー(笑い)。打ち直しの11打目をグリーン奥に打って2パット」。我を忘れる事態だっただけに、スコアの計算もおぼつかない。「同伴プレーヤーと15番のフェアウェイまで数えていて、ようやく『13』で落ち着いた」(中嶋)
初日の「80」に続き、2日目も80。中嶋のマスターズ初挑戦は、13番でのワースト記録とともに、ショッキングな結果に終わった。当時、傷心の中嶋は「一刻も早くオーガスタを離れたい」と語り同行した加納徹也氏(ゴルフリポーター)とともにアトランタ空港まで車を走らせ、一夜を明かすことになる。「勉強のために残る、というのは許されない雰囲気でもあったよね。親父(父・巌氏=故人)から早く帰って来いと言われたし」。
中嶋はオーガスタに足を踏み入れた時から、大きなショックに見舞われていた。「親父の元でやって来て、夢にまで見たマスターズに出られた。でも実際に行ってみると衝撃だった」。練習場で目の当たりにした世界のレベルの高さに圧倒されてしまった。
「選手たちは150ヤードから250ヤードまでの落下地点にキャディを立たせて、当たり前のように打っていた。正確無比で精度とパワーが圧倒的に違う。自分は短いクラブはできるけど、長いクラブになるとボールはあちこちに散らばるから恥ずかしくて、みんながいないところでしか練習できなかった」。
中島にとって、初めてのマスターズを戦うまでに経験した海外の試合は、前年11月にフロリダで開催されたダブルス戦と、マスターズ前の2月にペブルビーチなどで開催されたビング・クロスビープロアマの2試合のみ。経験の浅さが、大叩きの原因となっていたのは明らかだった。
帰国すると不屈の闘志で再起し、課題に取り組むこととなる。それは4か月後、聖地セントアンドリュースで行われた全英オープンで早くも実を結びかけた。中嶋は3日目の16番を終えてトップタイの大健闘を演じるまでになっていた。ところがここでまた、悪夢のような出来事が起こった。
鉄道跡の道(ロード)が走り、右サイドのオールドコースホテルの敷地に向かって打って行く通称ロードホールの17番。中嶋は手堅く2オンを果たしたが、ギャラリーはここから驚きの光景を目にすることになる。
再び中嶋の回想。「一緒に回っていたのはトム・ワイスコフ。2段グリーンの右手前に乗ったんだけど、上の段のピンまで20メートルくらいあった。2段グリーンを斜めに上がっていかなければいけないファーストパットは当たりそこないで、手前で左に曲がりグリーンを出て、バンカーに入ってしまった。『嘘だろ』という思いだった」。4打目となるバンカーショットはいったん脱出するものの、グリーン手前の傾斜に止まってからゆっくりとバンカーへと戻ってくる。5打目も同じようにバンカーへと戻り、6打目も…。結局7打目でようやくピンの奥に止まったが、2パットの「9」を叩いてしまう。
バンカー内で4打を叩いての「9」も伝説となり、ロードバンカーは別名「トミーズ・バンカー」とも呼ばれるようになった。23歳でオーガスタナショナル、セントアンドリュースという名コースで受けたあまりに過酷な試練を、中嶋はどう受け止めていたのか。
「その晩はホテルに帰って、ベッドを思い切り蹴り上げるほど、情けなくて悔しかった。でも13を叩いたマスターズからわずか4カ月後の全英で、予選から行って、出られて、優勝争いまでできたんだよ。努力が早くも開花したことで、『意外と世界は近いじゃん』と思えたのも事実。優勝争いからは脱落したけど、最終日にあこがれのアーノルド・パーマーと回れたことは大きかった。パーマーは特別な存在だったんだ。後にも先にも、サインをもらったのはこの時のパーマーだけだから。いいかと思っていたら17番で叩かれて、へこんで意気消沈してたけど、パーマーに救われた感じだった。パーマーの前でいい加減なゴルフはできないしね」
このメジャー2試合の経験で、課題も明確になった。「結局のところ、経験不足が原因なのよ。セントアンドリュースの3打目のファーストパットも、本人はピタッとつけるもんだと思っている。でも経験を積んでくれば、あれは1ピン程度によればいいと割り切れるから、間違ってもファーストパットをバンカーに入れてしまうなんてことは起こりえない。“足る”を知らないわけよ」。
それから8年――。中嶋は多くの経験を積んで、オーガスタでもその実力をいかんなく発揮するようになる。特に1986年のマスターズは、最も優勝に近づいた試合だった。
初日は2アンダーの「70」で回り、首位のビル・クラッツアートとケン・グリーンに2打差の5位でスタートした。2日目は通算5アンダーで首位に立ったセベ・バレステロスから2打差の3位。そして3日目は、通算6アンダーで首位に立ったグレッグ・ノーマンに、やはり2打差の6位タイで最終日を迎えた。
最終日の前半9ホールを終えて、中嶋は1オーバーの37。トム・ワトソンと同じ3アンダーでサンデーバックナインに突入した。首位をいくジャック・ニクラウスとノーマンとは、ここで2打差とあって、勝機は十分にあった。
しかし中嶋は、ここでオーガスタが持つ本当の怖さを実感することになる。結局バックナインは35に終わり、優勝したニクラウスからは5打遅れての8位フィニッシュ。「オーガスタのサンデーバックナインの厳しさを実感した。そこは本当に苦しかった。それを知っているだけに、松山(英樹)がバックナインを抜けてきた時に(実況席で)涙をこらえきれなかったんだ」と中嶋はしみじみとした口調で振り返った。
とはいえだ。23歳の時には初日、2日目と80を叩き、全く歯が立たなかった中嶋が、31歳となり大きく成長したことを、この年、オーガスタのパトロンたちに証明して見せた。
さらに4か月後。ターンベリーで行われた「全英オープン」でも、初日こそ4オーバーの「74」を叩き出遅れたものの、2日目に「67」をマークして首位のノーマンから4打差に迫る。3日目も「71」で踏ん張り、首位のノーマンに1打差の2位に浮上。全英オープンの大舞台で、最終日最終組をラウンドすることになったのだ。
しかしここでも、勝利の女神は中嶋に微笑まなかった。「自分のミスで負けた。自滅で崩れた」(中嶋)最終日は77を叩き、結局マスターズと同じく8位タイに終わり、優勝したノーマンを祝福する立場となってしまった。囲み取材では人目もはばからず、号泣することになる。「松山も(2017年の)全米プロゴルフ選手権でジャスティン・トーマスに負けて号泣したよね。同じ自滅の形だっただけに、あのシーンも(自分に)ダブるんだよ」。
この後、中嶋は律子夫人とともに、重い足取りでホテルの階段を上っていく。その時、自分に向けてバグパイプの演奏が行われているのに気づく。「200人ぐらいの宿泊客が、我々に向かって拍手を送ってくれていた。後ろを振り返っても、誰もいない。敗者に対する思いやりだと、その時分かった。勝者だけじゃなく、敗者も大事なんだ、という気持ちが伝わってきたよね」。
かつてオールドコースのバンカーで4度も叩き、トップタイの座から転落していった23歳の若者が、31歳になって優勝争いをしたことを、スコットランドの多くのファンが知っていた。健闘をねぎらう拍手と歓声が、中嶋夫妻を優しく包んでいた。
メジャー挑戦の歴史を振り返り、中嶋が言う。「やっぱり今の自分を作ってくれたのは、13を叩いたマスターズ。あそこが原点です。あの後、2通りのパターンがあったと思う。もう世界をあきらめるか、もう一度世界を知った上で目指すのか。幸いにして自分は後者になれたよね。親父が課題を出してくれたこともあって、世界の現実を練習に生かして、自分を変えなきゃいけない、と思えた。それが1986年のマスターズと全英での優勝争いにつながったのだと思う。負けたままで終わらなかったのは…。歩みを止めないことが大切なんだと思うよ」。
いかなるショックに見舞われても、挑戦を続けること。そこで得た苦い経験も、知識とともに自分の中に取り込んでいく。そのことの大切さを、優勝には手が届かないながらも中嶋はメジャーの舞台において優勝争いをすることで証明した。いずれも、中嶋常幸の血肉となった名勝負だったのは間違いない。(取材・構成=日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川朗)