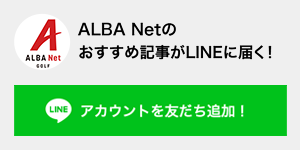悲報が尾崎将司・健夫・直道の3兄弟に届いたのは、1991年12月4日。日本シリーズの開幕前日のことだった。父・実さんが急性心不全のため76歳で急逝したとの報せだった。
通夜は故郷・徳島県海部郡宍喰町で、大会初日の夜に行われることが決まっていた。喪主を務める長男・ジャンボと二男・健夫は欠場を決め実家に戻ることを決めたが、末弟の直道は前週のカシオワールドオープンで優勝を飾り、賞金ランク2位に浮上したタイミング。初めての賞金王が、日本シリーズと大京オープンの残り2戦にかかっていた。
3兄弟が全員欠場しては、大会にも迷惑がかかる、との配慮も働いた。直道が、当時の複雑な思いを語る。「僕は身内の死とかは、ゴルフよりも絶対に大事だと思っているんで、当然宍喰に帰るつもりでいた。でも気が付いたら、ジャンボもジェットも参加メンバーから抜けてしまうわけ。これはまた相当な穴を空けることになるな、ということで“(直道に)やってみないか?”という話になった。でもやっぱり親父と会いたい。死に顔を見てからじゃないと、と思って何とか帰る方法はないか、と考えたの。そうしたら主催者の読売さんがヘリコプターを用意してくれるということになったんだよね」。
初日の開会式。ジャンボとジェットは不在ながら、参加選手全員が1分間の黙とうを捧げてくれた。しかし直道も、初日のゴルフまでは思うに任せない。当時の取材ノートには、直道のこんなコメントが記されている。
「やるしかない、と思っても、プレー中にはふっと心によぎるものがあったりして集中できなかった」
1アンダー、15位発進。首位の倉本昌弘、吉村金八は6アンダー。いきなり2人から5ストローク置いて行かれた。直道はその足で羽田空港へと向かい、徳島へ。父との対面が出来た時には、午後9時半をすぎていた。
2日目のスタート時間はワンウェイの4組目となる10時25分と決まっていた。「親父と会ってから、お袋の隣で寝たんだけど、ほとんど寝てない感じだよね。朝5時に起きて7時半くらいの便に乗って、羽田に到着。よみうりの9番に降りることになるんだけど…。ヘリコプターから見たコースが、自分には戦場に見えちゃったんだよ。それは今でも覚えている」。
移動距離は一晩で1960キロ。睡眠時間は2日間で2時間程度。疲れていないはずがなかった。「初日はもうほんとにダメで、1アンダーしか出なくて、2日目ももう全然寝ていないし、たぶん無理だろうと思ってんのに…。なぜかうまく行くんだよ」。
象徴的だったのは15番のパー3。宍喰では、午後1時からの告別式が始まろうとしている頃だった。5番アイアンのティショットが、入れてはいけないグリーン右のバンカーにつかまる。カップまでおよそ12メートル。しかもエッジから下ってわずか5ヤードの所にカップが切ってあり「パーを拾えるかどうか、ものすごく難しい状況だった」(直道)。しかし、このショットがものの見事にカップへと吸い込まれた。値千金のバーディ。2日目は7バーディ、「65」のベストスコア。気が付けば、トータル8アンダーで横島由一、湯原信光と並んでトップタイに浮上していた。
「満身創痍なのは間違いない。でも嘘と思いながらもいいスコアが出て、また頑張ろうという気持ちが湧いてきた」直道は、3日目も1イーグル、6バーディ、2ボギーの「66」で連日のベストスコア。トータル14アンダーまでスコアを伸ばし、2位の湯原に3打差をつけて最終日に突入することとなった。
父を失い、ジャンボブラザースの思いを背負って一人戦う直道。その姿が共感を呼び、最終日は前年の1万9365人を大きく上回る2万5542人と大会史上最高記録を塗り替える大ギャラリーが詰めかけた。
人、人、人…。コースを取り巻くギャラリーの前で、トップを走り続ける直道。歩く姿を見ても、疲れていることは明らかだった。「4日目は、やっぱり優勝は意識するわね。悲壮感いっぱいの顔で、必死の形相でプレーしていたと思う」。そんな直道に「忘れもしない」シーンがやってくる。6番、2打目が打ち下ろしとなる541ヤードのパー5。2番、4番のバーディで追撃ムードの中嶋常幸が、このホールのティショットを左の林にぶち込む。行ってみると、OBラインをわずかに越えたところに入っていた。この試合を含めた2試合で逆転賞金王への可能性を残している中嶋にとって、このOBは痛恨のものとなる。
一方、直道もフェアウェイから3番ウッドで2打目を放った瞬間、その顔から血の気が引く。ボールは左の林、OBゾーンに向かって飛び出したからだ。次の瞬間「カーン!」という乾いた音がコースに響き渡った。少し間があって、ボールは生き物のように林から出てきて、グリーン手前の花道、絶好のポジションに止まった。
「正直『やっちゃった』と思った。でもあれが花道に戻ってきて、初めて、ああ、親父がいてくれるんだな、と思ったよね。ただツキがあるっていうだけじゃなくてね。その後もポンポンパットが入った」。象徴的だったのが13番のパー4。カップまでおよそ25メートルは、あった。グリーンはうねり。3パットの恐れまであるラインを、ボールは吸い寄せられるように転がっていき、カップに消えた。
最終ホールを迎えた時、2位の湯原との差は7、中嶋との差は8まで開いていた。ウイニングパットを決めた直道は、ここでしか味わえない経験をする。「ホールアウトした瞬間、親父の顔が出てきたんだよね。そういうドラマチックな体験だから、やっぱりこれが自分の一番(の試合)になるのかな」。
それはそうだろう。あの最終日、コースに詰めかけた2万5千余のギャラリーはもとより、大会関係者も、そこにいるすべてが、直道の置かれている事情を知っていた。誰もが、直道の優勝を期待している。それに応えねばならない重圧は、並大抵のものではなかったはずだ。
そんなムードを、最も敏感に感じていたのはともに戦う選手たち。「一緒に回る選手たちもやりにくかったと思う。だから2日目からは『気にしないでね』とは言っていたんだけど」。様々な人々の、様々な思いが込められた「主役・尾崎直道」のドラマは完結した。
直道は最後に、こう語った。「ファンの人も、一番印象に残っている試合はこれだという人が多いよね。日本オープンに連勝しているのにさ」と言ってから、こう締めくくった。「良く勝てたなっていう思いは強いよ。自分がスゴイっていうんじゃなくて、親父がスゴイっていう感じだよね」。(取材・構成=日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川 朗)
通夜は故郷・徳島県海部郡宍喰町で、大会初日の夜に行われることが決まっていた。喪主を務める長男・ジャンボと二男・健夫は欠場を決め実家に戻ることを決めたが、末弟の直道は前週のカシオワールドオープンで優勝を飾り、賞金ランク2位に浮上したタイミング。初めての賞金王が、日本シリーズと大京オープンの残り2戦にかかっていた。
3兄弟が全員欠場しては、大会にも迷惑がかかる、との配慮も働いた。直道が、当時の複雑な思いを語る。「僕は身内の死とかは、ゴルフよりも絶対に大事だと思っているんで、当然宍喰に帰るつもりでいた。でも気が付いたら、ジャンボもジェットも参加メンバーから抜けてしまうわけ。これはまた相当な穴を空けることになるな、ということで“(直道に)やってみないか?”という話になった。でもやっぱり親父と会いたい。死に顔を見てからじゃないと、と思って何とか帰る方法はないか、と考えたの。そうしたら主催者の読売さんがヘリコプターを用意してくれるということになったんだよね」。
初日の開会式。ジャンボとジェットは不在ながら、参加選手全員が1分間の黙とうを捧げてくれた。しかし直道も、初日のゴルフまでは思うに任せない。当時の取材ノートには、直道のこんなコメントが記されている。
「やるしかない、と思っても、プレー中にはふっと心によぎるものがあったりして集中できなかった」
1アンダー、15位発進。首位の倉本昌弘、吉村金八は6アンダー。いきなり2人から5ストローク置いて行かれた。直道はその足で羽田空港へと向かい、徳島へ。父との対面が出来た時には、午後9時半をすぎていた。
2日目のスタート時間はワンウェイの4組目となる10時25分と決まっていた。「親父と会ってから、お袋の隣で寝たんだけど、ほとんど寝てない感じだよね。朝5時に起きて7時半くらいの便に乗って、羽田に到着。よみうりの9番に降りることになるんだけど…。ヘリコプターから見たコースが、自分には戦場に見えちゃったんだよ。それは今でも覚えている」。
移動距離は一晩で1960キロ。睡眠時間は2日間で2時間程度。疲れていないはずがなかった。「初日はもうほんとにダメで、1アンダーしか出なくて、2日目ももう全然寝ていないし、たぶん無理だろうと思ってんのに…。なぜかうまく行くんだよ」。
象徴的だったのは15番のパー3。宍喰では、午後1時からの告別式が始まろうとしている頃だった。5番アイアンのティショットが、入れてはいけないグリーン右のバンカーにつかまる。カップまでおよそ12メートル。しかもエッジから下ってわずか5ヤードの所にカップが切ってあり「パーを拾えるかどうか、ものすごく難しい状況だった」(直道)。しかし、このショットがものの見事にカップへと吸い込まれた。値千金のバーディ。2日目は7バーディ、「65」のベストスコア。気が付けば、トータル8アンダーで横島由一、湯原信光と並んでトップタイに浮上していた。
「満身創痍なのは間違いない。でも嘘と思いながらもいいスコアが出て、また頑張ろうという気持ちが湧いてきた」直道は、3日目も1イーグル、6バーディ、2ボギーの「66」で連日のベストスコア。トータル14アンダーまでスコアを伸ばし、2位の湯原に3打差をつけて最終日に突入することとなった。
父を失い、ジャンボブラザースの思いを背負って一人戦う直道。その姿が共感を呼び、最終日は前年の1万9365人を大きく上回る2万5542人と大会史上最高記録を塗り替える大ギャラリーが詰めかけた。
人、人、人…。コースを取り巻くギャラリーの前で、トップを走り続ける直道。歩く姿を見ても、疲れていることは明らかだった。「4日目は、やっぱり優勝は意識するわね。悲壮感いっぱいの顔で、必死の形相でプレーしていたと思う」。そんな直道に「忘れもしない」シーンがやってくる。6番、2打目が打ち下ろしとなる541ヤードのパー5。2番、4番のバーディで追撃ムードの中嶋常幸が、このホールのティショットを左の林にぶち込む。行ってみると、OBラインをわずかに越えたところに入っていた。この試合を含めた2試合で逆転賞金王への可能性を残している中嶋にとって、このOBは痛恨のものとなる。
一方、直道もフェアウェイから3番ウッドで2打目を放った瞬間、その顔から血の気が引く。ボールは左の林、OBゾーンに向かって飛び出したからだ。次の瞬間「カーン!」という乾いた音がコースに響き渡った。少し間があって、ボールは生き物のように林から出てきて、グリーン手前の花道、絶好のポジションに止まった。
「正直『やっちゃった』と思った。でもあれが花道に戻ってきて、初めて、ああ、親父がいてくれるんだな、と思ったよね。ただツキがあるっていうだけじゃなくてね。その後もポンポンパットが入った」。象徴的だったのが13番のパー4。カップまでおよそ25メートルは、あった。グリーンはうねり。3パットの恐れまであるラインを、ボールは吸い寄せられるように転がっていき、カップに消えた。
最終ホールを迎えた時、2位の湯原との差は7、中嶋との差は8まで開いていた。ウイニングパットを決めた直道は、ここでしか味わえない経験をする。「ホールアウトした瞬間、親父の顔が出てきたんだよね。そういうドラマチックな体験だから、やっぱりこれが自分の一番(の試合)になるのかな」。
それはそうだろう。あの最終日、コースに詰めかけた2万5千余のギャラリーはもとより、大会関係者も、そこにいるすべてが、直道の置かれている事情を知っていた。誰もが、直道の優勝を期待している。それに応えねばならない重圧は、並大抵のものではなかったはずだ。
そんなムードを、最も敏感に感じていたのはともに戦う選手たち。「一緒に回る選手たちもやりにくかったと思う。だから2日目からは『気にしないでね』とは言っていたんだけど」。様々な人々の、様々な思いが込められた「主役・尾崎直道」のドラマは完結した。
直道は最後に、こう語った。「ファンの人も、一番印象に残っている試合はこれだという人が多いよね。日本オープンに連勝しているのにさ」と言ってから、こう締めくくった。「良く勝てたなっていう思いは強いよ。自分がスゴイっていうんじゃなくて、親父がスゴイっていう感じだよね」。(取材・構成=日本ゴルフジャーナリスト協会会長・小川 朗)