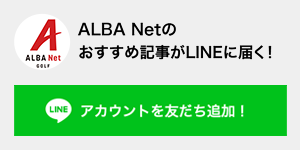プロゴルファーの多くが、試合以外に大きな“勝負”を経験している。プロのライセンスを手にするためのプロテストがそれだ。「2度と経験したくない」と多くのプロが口をそろえる緊張感。1999年賞金女王の村口史子が、プロになるために通らなければならなかった“最初の勝負”を振り返る。
すでに1次が始まっている2021年度女子のプロテスト。2次を経て11月に最終テストが行われ、20位タイまでが合格し、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)会員となることができる。現在とはシステムが違うが、村口が合格したのは1990年春のプロテストだ。
「あれだけ緊張することは、その後もなかった」と、その独特な空気を、村口は今でも覚えている。高校卒業後、一般企業のOLとなったが、3か月で退職。グリップの握り方もろくに知らないうちからプロゴルファーを志した。郡司洋プロに弟子入りして千葉CC野田に入社。練習を重ねて1990年に合格し、晴れてプロとなった。5回目の挑戦だった。
師匠からは「(千葉CCには)5年しか置かない」と言われており、この年、入社して5年目。ギリギリ、最後のチャンスだった。
「試合なら、また次もある。でも、プロテストに受からなかったら人生終わりだと思っていた。緊張しました。それまでにプロになれない先輩もたくさん見ていました。プロになるかならないかで、これほど変わるんだ、と言うことも見ていたので」。同様の言葉は、多くのプロが口にしている。現在以上に当時はプロと研修生の間にはハッキリと線引きがされており、差が大きかった。
経験を積めば積むほど、いい記憶も悪い記憶も染みついて行くのがゴルフというスポーツだ。プロテストの回数を重ねることによって、経験値は上がるが、悪い記憶も澱のように蓄積される。自信もつけば、苦しくもなる。そのことを徐々にわかっていた頃でもあった。
当時は春と秋、年に2回、開催されて、3日間トータル12オーバーまででプレーすれば、何人でも合格できた。当時は、地区ごとの研修会上位に入れば、プロテストに進めた。
ゴルフを全く知らないまま研修生となり、男子に混じって練習を続け、2年半ほどでプロテストを受けた。だが、そこからが長かった。
それでも、この年は自分のコースでプレーしてもいい感触があった。「セカンドショットが入るような流れのいいこともあったし、先輩からも『今年はイケるよ』と言われたりしていました」と矢板カントリークラブ(栃木県)での本番に挑んだ。
とはいえ、ゴルフ歴はわずかに5年。「何の裏付けもなく、気持ちだけでやるようなものでした」だけに、スタートしてみると波乱万丈のプレーぶり。「初日は、スタートのパー5でサードショットが入っていきなりイーグル。でも次のホールでティーショットをミスしてダボを叩いて吐き出してしまいました。その後もバーディ、ボギーとドタバタでした。悪い記憶はもちろん途中でよみがえりました。(以前)フェアウェイでボールが止まったのに、後ろに石があって打てないアンラッキーで、ショックだったこととかが頭の片隅にある。色々思い出したけど、とりあえず頑張って目の前のボールを打つしかなかった」と、必死の戦いが続く。
「確か3オーバー、3オーバーの(トータル)6オーバーで最終日になったと思うんですけど。朝から本当に緊張しました」。クラブハウスの食堂で朝食を摂っても「食べ物が胃から出てきちゃう感じ」と、ヒリヒリするような緊張感を抱えてスタートして行った。
前半はパープレー。トータル6オーバーで残り9ホール。この時「後半6オーバーでも(トータル12オーバーで)大丈夫なんだな、と思ったら、ハーフなのにウルウル来ちゃって」と苦笑する。
後半は、結局、3オーバーでプレーして、トータル9オーバー。「18番からクラブハウスに向かうエスカレーターを昇りながら『次は試合に出るんだ』という気持ちになったのを覚えています。だから涙は出なかったですね」。20位タイまで、とライバルたちのスコアに左右される現在と違い、スコアだけで合否が決まったため、一緒にプレーしている仲間たちと励まし合いながらプレーできたことも大きかったと言う。
「ゴルフ人生最初の勝負でした」。村口は5度目で、この”勝負”に勝った。システムは違っても、今年もまたこのとてつもない緊張感に挑む後輩たちがいる。先輩たちが感じたのと同じヒリヒリする空気を味わい、狭き門を目指して。(文・小川淳子)
すでに1次が始まっている2021年度女子のプロテスト。2次を経て11月に最終テストが行われ、20位タイまでが合格し、日本女子プロゴルフ協会(JLPGA)会員となることができる。現在とはシステムが違うが、村口が合格したのは1990年春のプロテストだ。
「あれだけ緊張することは、その後もなかった」と、その独特な空気を、村口は今でも覚えている。高校卒業後、一般企業のOLとなったが、3か月で退職。グリップの握り方もろくに知らないうちからプロゴルファーを志した。郡司洋プロに弟子入りして千葉CC野田に入社。練習を重ねて1990年に合格し、晴れてプロとなった。5回目の挑戦だった。
師匠からは「(千葉CCには)5年しか置かない」と言われており、この年、入社して5年目。ギリギリ、最後のチャンスだった。
「試合なら、また次もある。でも、プロテストに受からなかったら人生終わりだと思っていた。緊張しました。それまでにプロになれない先輩もたくさん見ていました。プロになるかならないかで、これほど変わるんだ、と言うことも見ていたので」。同様の言葉は、多くのプロが口にしている。現在以上に当時はプロと研修生の間にはハッキリと線引きがされており、差が大きかった。
経験を積めば積むほど、いい記憶も悪い記憶も染みついて行くのがゴルフというスポーツだ。プロテストの回数を重ねることによって、経験値は上がるが、悪い記憶も澱のように蓄積される。自信もつけば、苦しくもなる。そのことを徐々にわかっていた頃でもあった。
当時は春と秋、年に2回、開催されて、3日間トータル12オーバーまででプレーすれば、何人でも合格できた。当時は、地区ごとの研修会上位に入れば、プロテストに進めた。
ゴルフを全く知らないまま研修生となり、男子に混じって練習を続け、2年半ほどでプロテストを受けた。だが、そこからが長かった。
それでも、この年は自分のコースでプレーしてもいい感触があった。「セカンドショットが入るような流れのいいこともあったし、先輩からも『今年はイケるよ』と言われたりしていました」と矢板カントリークラブ(栃木県)での本番に挑んだ。
とはいえ、ゴルフ歴はわずかに5年。「何の裏付けもなく、気持ちだけでやるようなものでした」だけに、スタートしてみると波乱万丈のプレーぶり。「初日は、スタートのパー5でサードショットが入っていきなりイーグル。でも次のホールでティーショットをミスしてダボを叩いて吐き出してしまいました。その後もバーディ、ボギーとドタバタでした。悪い記憶はもちろん途中でよみがえりました。(以前)フェアウェイでボールが止まったのに、後ろに石があって打てないアンラッキーで、ショックだったこととかが頭の片隅にある。色々思い出したけど、とりあえず頑張って目の前のボールを打つしかなかった」と、必死の戦いが続く。
「確か3オーバー、3オーバーの(トータル)6オーバーで最終日になったと思うんですけど。朝から本当に緊張しました」。クラブハウスの食堂で朝食を摂っても「食べ物が胃から出てきちゃう感じ」と、ヒリヒリするような緊張感を抱えてスタートして行った。
前半はパープレー。トータル6オーバーで残り9ホール。この時「後半6オーバーでも(トータル12オーバーで)大丈夫なんだな、と思ったら、ハーフなのにウルウル来ちゃって」と苦笑する。
後半は、結局、3オーバーでプレーして、トータル9オーバー。「18番からクラブハウスに向かうエスカレーターを昇りながら『次は試合に出るんだ』という気持ちになったのを覚えています。だから涙は出なかったですね」。20位タイまで、とライバルたちのスコアに左右される現在と違い、スコアだけで合否が決まったため、一緒にプレーしている仲間たちと励まし合いながらプレーできたことも大きかったと言う。
「ゴルフ人生最初の勝負でした」。村口は5度目で、この”勝負”に勝った。システムは違っても、今年もまたこのとてつもない緊張感に挑む後輩たちがいる。先輩たちが感じたのと同じヒリヒリする空気を味わい、狭き門を目指して。(文・小川淳子)