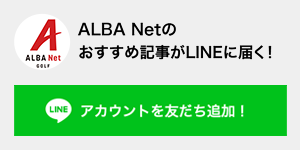敗北やから多くを学び、後の自分の糧とする。勝負の世界で大切な子のことを、村口史子は経験している。1999年に賞金女王を手にするエネルギーにもなった忘れられない悔しさは、1998年ヤクルトレディースにあった。
OLから一念発起して5年でプロゴルファーに転身。1990年にデビューした直後、村口はそんな珍しい経歴で注目されていた。以来7年間、ツアーで実績を積み、通算4勝。特に1997年には初めて賞金ランキング9位。満を持して臨んだのが、1998年シーズンだった。
シーズン9試合目のこの大会までの成績は、予選落ちは2度あるが、それ以外はまずまず。トップ10にも1回は入っている。序盤戦を終え、いよいよ選手たちにエンジンがかかり始める5月半ば。福岡国際CC(福岡)を舞台にした同大会初日は、1オーバー26位タイ。首位の金愛淑(韓国)、岡田美智子とは3打差と、悪くないスタートだ。
女子プロ1期生の岡田の名前を見てもわかるように、まだまだツアー黎明期のベテランが存在感を示す中、若手がその牙城を切り崩していった頃。現在のツアーとは違い、31歳の村口も若手の一角を担っていた。
1アンダーでプレーしてトータルイーブンパーとした2日目は8位タイに浮上、一方で、首位となった武田久子との差は4打差となっていた。
迎えた最終日は大激戦となる。途中、高須愛子が首位に立つが、そこから崩れてトータル3アンダー。4バーディ、1ボギーでプレーした村口を含め、3人がトータル3アンダーでプレーオフに突入する。相手は、ツアー通算17勝、45歳のベテラン高須と、シード3年目で27歳、未勝利だが、この日、5バーディと好調な山田かよだ。
村口は、プロ7年目にしてはゴルフ経験が少ない。何しろ、OL時代にゴルフに触れた瞬間、プロになることを決意。ろくろくグリップもきちんと握れないうちに「プロになりたいんです」と、後に師匠となる郡司洋に頭を下げて呆れられた逸話を持つほどだ。5年間の期限付きで千葉の研修生となり、期限ぎりぎりでプロテストに合格している。プロになり、すぐに試合に出始めたこともあり、ツアーになかったマッチプレーの経験は持っていなかった。サドンデスのプレーオフは、感覚としてはマッチプレーに近い。生まれて初めてのプレーオフだった。
村口同様、プレーオフ初体験だった山田が、1ホール目でボギーを叩いてまず脱落。高須と2人の戦いとなった2ホール目、村口はパーオンしたものの、このバーディパットを打ちきれず、ショートしてしまう。「乗ったけど遠目だった。8メートル?うーん、10メートルくらいあったかもしれません。狙ってかなきゃ、と思ったけど手が動かなくてビビっちゃった」。直後に、高須がバーディパットを沈めるのを、指をくわえて見ているしかなかった。高須は「村口さんのラインが参考になりました」というコメントまで残している。
すぐそこまで手繰り寄せながら、スルリとこぼれたツアー5勝目。プレーオフにまで持ちこみながら、パットをショートして自ラ勝利を手放した記憶は、大きな悔しさとなって心に残る。「弱気になってしまった自分自身がイヤだった。眠れないくらい悔しかった。勝つのって、本当に大変だったなと思った試合でした」と、20年以上経った今でも、悔しそうな口調を隠そうともしない。これが、翌年、最高の形で生きることになる。
1年後の同じ舞台で、村口は、その悔しさを最高の形に変えることになる。最終日前半にスコアを伸ばし、山岡明美、不動裕理に2打差をつけて優勝。1年越しのリベンジを果たした。1998年は結局、未勝利に終わり、これが2シーズンぶりのツアー5勝目だった。
「実は最終日の前の晩に夢を見たんです。自分が優勝する夢。でも、プレー中は全然忘れていて、山岡さんとのマッチプレーのような感じで大変だった気がします。夢のことをを思い出したのは優勝してから」と笑う。
優勝へのカギは、前年プレーオフの反省を踏まえて、弱気にならないことに尽きる。このことは、シーズンを通して村口に大きな強さをもたらした。
翌週の中京テレビ・ブリヂストンオープンで続けて優勝。さらに8月の新キャタピラー三菱レディスでも勝って、初の賞金女王の座についた。頂点を極めた裏にあったのが、1998年ヤクルトレディースの悔しいプレーオフ負けだったのはまちがいない。結果的に、これが村口にとってツアーで最初で最後のプレーオフとなった。(文・小川淳子)
OLから一念発起して5年でプロゴルファーに転身。1990年にデビューした直後、村口はそんな珍しい経歴で注目されていた。以来7年間、ツアーで実績を積み、通算4勝。特に1997年には初めて賞金ランキング9位。満を持して臨んだのが、1998年シーズンだった。
シーズン9試合目のこの大会までの成績は、予選落ちは2度あるが、それ以外はまずまず。トップ10にも1回は入っている。序盤戦を終え、いよいよ選手たちにエンジンがかかり始める5月半ば。福岡国際CC(福岡)を舞台にした同大会初日は、1オーバー26位タイ。首位の金愛淑(韓国)、岡田美智子とは3打差と、悪くないスタートだ。
女子プロ1期生の岡田の名前を見てもわかるように、まだまだツアー黎明期のベテランが存在感を示す中、若手がその牙城を切り崩していった頃。現在のツアーとは違い、31歳の村口も若手の一角を担っていた。
1アンダーでプレーしてトータルイーブンパーとした2日目は8位タイに浮上、一方で、首位となった武田久子との差は4打差となっていた。
迎えた最終日は大激戦となる。途中、高須愛子が首位に立つが、そこから崩れてトータル3アンダー。4バーディ、1ボギーでプレーした村口を含め、3人がトータル3アンダーでプレーオフに突入する。相手は、ツアー通算17勝、45歳のベテラン高須と、シード3年目で27歳、未勝利だが、この日、5バーディと好調な山田かよだ。
村口は、プロ7年目にしてはゴルフ経験が少ない。何しろ、OL時代にゴルフに触れた瞬間、プロになることを決意。ろくろくグリップもきちんと握れないうちに「プロになりたいんです」と、後に師匠となる郡司洋に頭を下げて呆れられた逸話を持つほどだ。5年間の期限付きで千葉の研修生となり、期限ぎりぎりでプロテストに合格している。プロになり、すぐに試合に出始めたこともあり、ツアーになかったマッチプレーの経験は持っていなかった。サドンデスのプレーオフは、感覚としてはマッチプレーに近い。生まれて初めてのプレーオフだった。
村口同様、プレーオフ初体験だった山田が、1ホール目でボギーを叩いてまず脱落。高須と2人の戦いとなった2ホール目、村口はパーオンしたものの、このバーディパットを打ちきれず、ショートしてしまう。「乗ったけど遠目だった。8メートル?うーん、10メートルくらいあったかもしれません。狙ってかなきゃ、と思ったけど手が動かなくてビビっちゃった」。直後に、高須がバーディパットを沈めるのを、指をくわえて見ているしかなかった。高須は「村口さんのラインが参考になりました」というコメントまで残している。
すぐそこまで手繰り寄せながら、スルリとこぼれたツアー5勝目。プレーオフにまで持ちこみながら、パットをショートして自ラ勝利を手放した記憶は、大きな悔しさとなって心に残る。「弱気になってしまった自分自身がイヤだった。眠れないくらい悔しかった。勝つのって、本当に大変だったなと思った試合でした」と、20年以上経った今でも、悔しそうな口調を隠そうともしない。これが、翌年、最高の形で生きることになる。
1年後の同じ舞台で、村口は、その悔しさを最高の形に変えることになる。最終日前半にスコアを伸ばし、山岡明美、不動裕理に2打差をつけて優勝。1年越しのリベンジを果たした。1998年は結局、未勝利に終わり、これが2シーズンぶりのツアー5勝目だった。
「実は最終日の前の晩に夢を見たんです。自分が優勝する夢。でも、プレー中は全然忘れていて、山岡さんとのマッチプレーのような感じで大変だった気がします。夢のことをを思い出したのは優勝してから」と笑う。
優勝へのカギは、前年プレーオフの反省を踏まえて、弱気にならないことに尽きる。このことは、シーズンを通して村口に大きな強さをもたらした。
翌週の中京テレビ・ブリヂストンオープンで続けて優勝。さらに8月の新キャタピラー三菱レディスでも勝って、初の賞金女王の座についた。頂点を極めた裏にあったのが、1998年ヤクルトレディースの悔しいプレーオフ負けだったのはまちがいない。結果的に、これが村口にとってツアーで最初で最後のプレーオフとなった。(文・小川淳子)