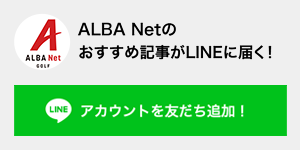「さあ、みんな、このブルックス・カップケーキをみんなで食べてしまえ!」
そう言いながらデシャンボーはカップケーキを人々に手渡し、驚くなかれ、ケプカにも「はい、どうぞ」。ケプカは「何が乗っかってるんだ? とんでもないカップケーキだ」と怒声を上げつつ、パクリ。見つめていた人々は大喜びで拍手喝采。ほとんどプロレス的な「ショー」の雰囲気だ。だが、そもそもTVマッチはまさにショーであり、プロゴルフもスポーツであると同時にショーであることを誰もが理解して納得できているからこそ、成立する笑いである。
デシャンボーが、たとえばクッキーなどではなくカップケーキを持ち出した理由は、ある年のフェニックス・オープンのスタートホールで、選手を紹介するスターターがケプカを「ブルックス・カップケーキ」と間違えて呼んだことがあったからで、そのときケプカは、スターターのミスを一笑に付し、ギャラリーも大笑いした。
その後、米メディアはその出来事をすぐに逆手に取り、「アナウンス間違い特集」を作ってオンエアした。そこに出てきた名前の誤りは、「ブルックス・カップケーキ」を筆頭に、ダスティン・ジョンソンが「ジャスティン・ドンソン」となり、ジェイソン・デイが「ジョーダン・デイ」、ジミー・ジョンソンが「ジミー・ファウラー」、丸山茂樹は「シゲキ・マリファナ」になってしまっていた。だが、そうしたことに目くじらを立てるのではなく、本人もみんなもワッハッハッと笑い飛ばす。そういう土壌があるからこそ、今回の「犬猿マッチ」が成立したのだろう。
そのまま真似をしても、国民性や文化、社会の土壌が違えば、必ずしも笑いにはならないだろう。そうした文化をどう感じているかと問われたら、プロレスを見ていても「痛そう」「怖い」と感じて直視できない私は、たとえショー的な要素が強いとわかっていても、相手を露骨に“口撃”するやり取りは、どうも好きになれない。
だが、人々がケプカとデシャンボーの対決を楽しみ、ゴルフファンが少しでも増えたのなら、それはそれで、そういうやり方もあるのだなと頷くことはできる。ともあれ、デシャンボーから「ブルックス・カップケーキ」を差し出されたら、クスッと笑うぐらいの感覚は、私も持ち合わせている。
そう言いながらデシャンボーはカップケーキを人々に手渡し、驚くなかれ、ケプカにも「はい、どうぞ」。ケプカは「何が乗っかってるんだ? とんでもないカップケーキだ」と怒声を上げつつ、パクリ。見つめていた人々は大喜びで拍手喝采。ほとんどプロレス的な「ショー」の雰囲気だ。だが、そもそもTVマッチはまさにショーであり、プロゴルフもスポーツであると同時にショーであることを誰もが理解して納得できているからこそ、成立する笑いである。
デシャンボーが、たとえばクッキーなどではなくカップケーキを持ち出した理由は、ある年のフェニックス・オープンのスタートホールで、選手を紹介するスターターがケプカを「ブルックス・カップケーキ」と間違えて呼んだことがあったからで、そのときケプカは、スターターのミスを一笑に付し、ギャラリーも大笑いした。
その後、米メディアはその出来事をすぐに逆手に取り、「アナウンス間違い特集」を作ってオンエアした。そこに出てきた名前の誤りは、「ブルックス・カップケーキ」を筆頭に、ダスティン・ジョンソンが「ジャスティン・ドンソン」となり、ジェイソン・デイが「ジョーダン・デイ」、ジミー・ジョンソンが「ジミー・ファウラー」、丸山茂樹は「シゲキ・マリファナ」になってしまっていた。だが、そうしたことに目くじらを立てるのではなく、本人もみんなもワッハッハッと笑い飛ばす。そういう土壌があるからこそ、今回の「犬猿マッチ」が成立したのだろう。
そのまま真似をしても、国民性や文化、社会の土壌が違えば、必ずしも笑いにはならないだろう。そうした文化をどう感じているかと問われたら、プロレスを見ていても「痛そう」「怖い」と感じて直視できない私は、たとえショー的な要素が強いとわかっていても、相手を露骨に“口撃”するやり取りは、どうも好きになれない。
だが、人々がケプカとデシャンボーの対決を楽しみ、ゴルフファンが少しでも増えたのなら、それはそれで、そういうやり方もあるのだなと頷くことはできる。ともあれ、デシャンボーから「ブルックス・カップケーキ」を差し出されたら、クスッと笑うぐらいの感覚は、私も持ち合わせている。